インターネットで注文すると、こういった段ボールが届きますね。私たちの暮らしでは欠かすことのできない宅配便です。この仕組みを支えているのが、貨物列車なんですが、今、存続のピンチです。
札幌市豊平区の理容店です。
常に最新のヘアスタイルを提供している店長には、もうひとつ「最新」にこだわっているものが…
待ち合いコーナーに並べられたマンガ、週刊誌、ファッション誌。毎日発売される本の最新刊を揃えておくことです。
ヘアーサロンもんま 小原伸一 店長
「最新のヘアカタログとか雑誌を見てヘアスタイルのオーダーが多いので。週刊誌は出る日が決まっていて、(運んでいるのが)貨物列車なんだなというのを初めて本屋さんで知りました」
雑誌や週刊誌の多くは、首都圏で製本されます。1000キロ近く離れた道内でもすぐに読むことができるのは…貨物列車が運んでいるからです。
記者リポート
「本州から北海道には通販などの宅配便や郵便物、そして週刊誌などの書籍が運ばれて来ます。北海道から本州へはタマネギや、ジャガイモ、米などの農産物が送られます」
タマネギの生産量、日本一を誇る北海道北見地方。およそ20万トンのタマネギを、貨物列車で全国に出荷しています。
毎晩、北見市を出発する貨物列車は「タマネギ列車」とも呼ばれています。
JAきたみらい 大坪広則 組合長
「北見玉ねぎって名前も入っているし、やっぱり作っていて、安定供給するという責任を果たせるなと」
道内の農産物の多くは、貨物列車で本州方面に運ばれています。まさに貨物列車は「食料基地」の北海道と本州をつなぐ「大動脈」。しかし今、この生命線に「寸断」の危機が迫っています。
JAきたみらい 大坪広則 組合長
「この鉄路が無くなると、我々が作ったタマネギはどうするんだと」
JR函館線の函館・長万部間は、旅客列車とともに貨物列車が1日50本以上走る大動脈です。この区間に大きな問題が浮上しています。
記者リポート
「奥に見えるのは北海道新幹線の国縫トンネルです。札幌に向けて工事が進められています。そしてこちらは現役の函館本線です。新幹線と並ぶように走っているので並行在来線と呼ばれています」
2030年度に札幌に延伸される北海道新幹線。開業するとJR北海道は函館・小樽間のJR函館線を手放します。
大きな赤字を生んだ国鉄時代の反省から、JRは、儲かる見込みのない並行在来線から撤退できるルールなのです。
函館・長万部間の線路を存続させるか、廃止するかを決めるのは、道と沿線の7つの市と町。11年前から協議を続けていますが、利用者の増加が見込めない鉄道の維持にはどのマチもおよび腰です。
仮に沿線のマチが運営する「第3セクター」で鉄道を残した場合、30年間の累積赤字は800億円を超えると試算されています。
北海道長万部町 木幡正志 町長
「やっていけないですよ。だいたい3セクにしようが、何にしようが。地元負担が大きすぎる。年間にかかる工事費、災害対応、それから人員の支払いまで含めたら、これを小さな自治体の塊にやりなさいっていう方が無理があって…」
しかし、この線路が無くなると、本州への貨物列車も走れなくなり、物流の大動脈が断たれます。地元だけでは判断できず、結論を導き出せない要因です。
全国の「貨物列車」の運行を一手に引き受けるJR貨物。いっそ、JR貨物が並行在来線の経営を引き継ぎ貨物専用として使うことはできないのでしょうか。
JR貨物 北海道支社 安田晴彦支社長
「JR7社に分割されたときのルールとしてですね。線路を持つ旅客会社の線路の上を使うという仕組みでできた会社でありますので、弊社の要員などを見ますと、やはり弊社の方で線路を維持していくのは現実的ではないと思っています」
一方、危機的な経営が続くJR北海道。新幹線の開業を足掛かりに経営を立て直す計画があり、新幹線の運行に集中したい考えです。
JR北海道 綿貫泰之 社長(去年9月の記者会見)
「(並行在来線の)経営に参画することはありません。当社の経営から分離するので、経費の負担も無いと考えております」
線路は、絶対に必要。しかし140キロもの長距離で、海沿いの傷みやすい線路の維持費用を、誰が、どこまで負担するのか。
進まなかった議論に去年11月、国は道とJR貨物、JR北海道に呼びかけて話し合いを始めました。
鈴木直道 知事
「通勤、通学、観光、物流面から大きな役割を担っている線区であります。様々な協議検討していきたい」
北海道大学 公共政策大学院 岸邦宏 教授
「最後は誰かが負担しなければいけないわけですよね。貨物専用というような線路にもしもなったときに、それを維持する財源というのも、そもそも制度がない。北海道は当然恩恵があるでしょうし、食料の安全保障というところも考えると国全体にも恩恵がある。すると国がどれだけ、北海道はどれだけとか、負担の割合を決めていくところが、今、議論として進めなくてはいけないことだと思いますね」
モノがすぐに手に入り、安全な食材が食べられる、何気ない日常が失われるかもしれない。
「大動脈」を維持し続けることができるのか。地元だけの問題ではなく、私たちの暮らしにも暗い影を落としています。
1月30日(月)「今日ドキッ!」午後6時台
全国のトップニュース
女子団体パシュート、女王奪還ならずも銅メダル!髙木「すごく誇らしい」21歳・野明は涙「また強くなって戻ってこれたら」【ミラノオリンピック】

18日に衆院選後初の特別国会召集 第2次高市内閣発足へ

東広島市男性殺害事件 男性の死因は「失血死」 70人態勢で捜査本部を設置

死因は“刃物が心臓貫通”による心停止 岩崎龍我容疑者は確保の際「折り畳みナイフ」所持 大阪・道頓堀少年3人殺傷事件

米イラン核協議「指針となる原則で大枠合意」 主張に溝も「進展」とイラン外相

去年1年間の不正薬物の押収量2.7トン超で「過去最悪」 航空機旅客からの押収量が前年比約2.5倍で急増 東京税関
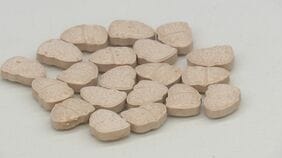
横浜・鶴見区で住宅5棟焼ける火事 80代男性が軽傷

「生きて戦っている」侵攻から4年 ウクライナ選手「任務に就くよう命じられ」競技諦める覚悟も再び挑戦 ミラノ・コルティナオリンピック

