こちらのカフェではご注文には少々時間いただきます。
JR札幌駅の近くにある人気スープカレー店です。黙々と手際よく調理しているのは、山崎佑基さん、24歳。北海道大学で空間デザインを研究する大学院生です。山崎さんはある苦労と共に生きています。「きつ音」です。
アルバイト先の店長は…。
奥芝商店 駅前創成寺店 桑原昇照店長
「面接段階からきっぱりと出来ればホールは出たくないと言われた」
山崎佑基さん
「客に対してなんでこの店員話せないんだろうというのもあるし」
山崎さんが、きつ音を気にするようになったのは、小学4年生の時。
山崎佑基さん
「学芸会の劇の発表練習の時に『あれ、全然言葉が出てこないな』と思って、それをきっかけに気にするようになりました」
以来、人前で話す事を避けるようになりました。
「きつ音」とは、話す時の最初の一音に詰まってしまうなど言葉が滑らかに出ない発話障害のひとつです。主な症状は3つで「こここ、こんにちは」と言葉のはじめの音を繰り返す「連発」。「こーーんにちは」と音が伸びてしまう「伸発」そして、うまく言葉が出ずに間が空いてしまう「難発」です。
国内に、およそ120万人、100人に1人いると言われるきつ音ですが、正しい理解が広がっていないため、当事者には「しゃべり方がおかしい」という偏見がぶつけられることも珍しくありません。
マンデーナイト吃音カフェ主催者 南孝輔さん
「堅苦しい集まりではなくて、きつ音について、自分のことについて、フランクに話し合える場所が欲しいと考えたのがきっかけですね」
札幌で、毎週月曜日に開かれている、きつ音当事者の集まりです。これまでの苦労話や思い出話を、「どもって」も気にせず、安心して話せる場所です。
参加者
「小学校入る頃には音読が苦痛だったので気付いた頃にはどもってた」
「友達としゃべって楽しい時の方がどもっちゃう」
「本当に(きつ音)?そんなことないと言われる。そんなことあるんだよって。説明のしようがない…」
語り合える仲間から、元気をもらいます。
札幌市の北海道大学。この日「1日だけ」のカフェがオープンしました。北海道内では初めての「注文に時間がかかるカフェ」です。
カフェ店員
「(コップを)お持ちいただけると、洗ってお持ち帰りできる形になっている」
この日、北大に「3時間だけ」のカフェがオープンしました。店員を務めるのは、山崎さんをはじめ、きつ音があり、札幌市内に住む4人の若者。主宰したのは、このカフェイベントを全国で開き、自分にもきつ音がある奥村安莉沙さんです。
注文に時間がかかるカフェ発起人 奥村安莉沙さん
「名前は『注文に時間がかかるカフェ』と言いまして、接客業に挑戦したくてもきつ音があって一歩踏み出せない若者が接客に挑戦することで自信をつけてほしい」
カフェでは「表示」を使って、客に「きつ音」について説明します。
山崎佑基さん
「緊張しているから、どもっているというわけではないので『リラックスして』『ゆっくり話せばいいよ』などのアドバイスはしないでいただけると有難いです」
さらに、こだわりは、スタッフのマスク。それぞれ、客にお願いすることが書かれています。
「話すのは苦手だけれども喋るのは好きなので気軽に話しかけて下さい」
「どもっても言葉が出てくるまで待っててくださいと書いてます」
注文に時間がかかるカフェ発起人 奥村安莉沙さん
「色々な症状、考え方があるので、まずはその人がどうしてほしいのかを聞いてもらえたら嬉しい」
そこには、きつ音というラベルを貼ることで、ひとまとめにはしないで欲しいという願いが込められています。「いらっしゃいませ」など、決まった言葉を言いづらい人もいるためマニュアルはなく、自分の言いやすい言葉で、時間をかけて接客します。
客
「息子にきつ音があるのでこういうイベントを体験してみたら、きつ音があるから出来ないと思わないでこういうことも出来るというのを生で見れたら違うのかなと思って来た」
「接客のアルバイトは難しいと昔から思っていたので、それをこう言った形でチャレンジできる場があるというのは素晴らしいと当事者として思う」
かつて、人前で話す事を避けていた山崎さん。現在は…。
山崎佑基さん
「それではお作りしますので、もう少々お待ちください」
時々どもりながらも接客。アルバイトやカフェでの接客経験を重ねることで、きつ音との向き合い方にも変化が。
山崎佑基さん
「どもってもお客さんは話を最後まで聞いてくれる。隠さずにやっていくことで周りの人にも受け入れてもらえる。知ってもらうだけでも僕ら(当事者)は働きやすいし生きやすいのかなと思う」
まず、きつ音について、知って欲しい。そこには、きつ音の陰に隠れず、自分の人生を堂々と生きる姿がありました。
12月14日(水)「今日ドキッ!」
全国のトップニュース
三浦璃来「いつも引っ張ってくれる龍一くんが…」りくりゅう大逆転Vの裏側明かす「今回は私がお姉さんでした(笑)」【ミラノ五輪】

【速報】詐欺容疑で逮捕、自宅調べると寝室に遺体が…2年以上、実母の遺体放置か 無職の57歳男を逮捕 福島

「旦那が中にいるので助けて」犯人“強い殺意”で犯行に…死亡した男性の首には切られたり刺されたような複数の傷 東広島市殺人事件

「生きて戦っている」侵攻から4年 ウクライナ選手「任務に就くよう命じられ」競技諦める覚悟も再び挑戦 ミラノ・コルティナオリンピック

あす(18日)特別国会召集 与野党新人・元議員が国会へ 暴言から9年…返り咲きも 自民党新人対象の研修会 「発言注意して」幹部が指導

死因は“刃物が心臓貫通”による心停止 岩崎龍我容疑者は確保の際「折り畳みナイフ」所持 大阪・道頓堀少年3人殺傷事件

“30年に一度レベル”記録的少雨 東北地方の太平洋側~九州南部で 「大規模な林野火災が起こりやすい状況」気象庁が注意呼びかけ
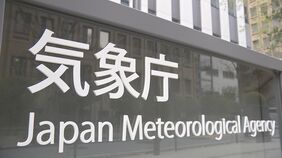
卵価格 過去最高値に並ぶ 1パック308円 平年より26%高い 鳥インフルエンザの影響…

