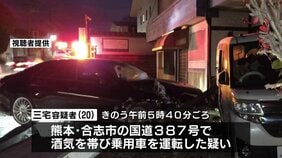「節分」といえば、病や災いを追い払い、福を呼び込む「豆まき」が定番ですが…。
伊藤亜衣記者
「ずっしり重たいです、いただきます」
もうひとつの定番が、この「恵方巻」です。
「恵方巻」が誕生したのは江戸時代から明治時代にかけてで、大阪の「丸かぶり寿司」がルーツといわれていますが、北海道内では、いつから食べられるようになったのでしょうか。
映像は、いまから26年前、1999年の北海道神宮です。
行われていたのは、恵方巻のルーツとされる「丸かぶり寿司」の無料配布。
その数、なんと1000本!受け取った人たちは、その場で恵方を向いて巻き寿司を頬張っています。
当時、イベントに協賛したという、のりメーカーに話を聞くことができました。
ホッカン 拝野智治執行役員
「開始時間が、もし8時からだとすると、(人が)6時ぐらいにもう並んでて、(丸かぶり寿司を)もらえる・もらえないで、けっこう殺気立っていた感じは覚えている」
イベントを手伝った経験がある拝野さんは、始まった当時、「恵方巻」はほとんど認知されていなかったと話します。
ホッカン 拝野智治執行役員
「当時、恵方巻は、のり業界でも知っていたけど大阪が発祥で、まだ大阪でしか盛り上がっていない行事だった。恵方巻を広めていきたいという活動の一環として、北海道神宮で恵方巻を無償配布することを始めたと聞いている」
イベントは、2007年頃に終了しましたが、コンビニなどでも売られるようになり「節分の恵方巻」は北海道内に広がりました。
ホッカン 拝野智治執行役員
「この恵方巻ができたおかげで多分1日でいうと、のりの出荷が一番多い日になっている状況。(節分は)われわれにとって、ある意味一番忙しいイベント」
全国のトップニュース
きょう日韓首脳会談 シャトル外交の一環 トランプ政権や中国含む地域情勢などへの対応めぐり連携確認へ

トランプ大統領 ノーベル平和賞のマチャド氏と15日に会談へ ベネズエラ情勢について協議

【速報】イランと取引のある国からの輸入品に25%の「二次関税」 トランプ大統領が「即時発効」と表明 イランへの経済的圧力を強化

小泉防衛大臣がきょうから就任後初のアメリカ訪問 ヘグセス国防長官との会談も予定 ベネズエラへの攻撃や中国についても意見交換か
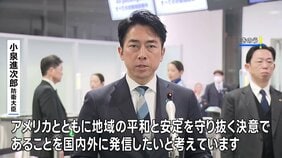
「今度はもっと良い仕事をしていきたい」 “ホテル密会”問題の小川晶氏が再選 前橋市長選挙

“1月解散”急浮上…高市総理の胸中は 「経済後回し解散」と野党は批判 街からは「解散」より「物価高対策」という声も…【news23】

ウクライナ侵攻 独ソ戦の日数1418日超え ゼレンスキー大統領「ロシアは20世紀に起きた最悪の出来事のほとんどを再現した」

「同窓会の帰りだった」酒気帯び運転の疑いで20歳男を現行犯逮捕 熊本