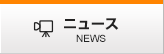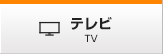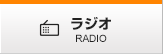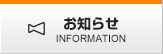掛け声にあわせ親指をあげ、その数を言い当てる遊び。皆さんはなんと呼んでいますか?
調べてみると、その呼び方や掛け声は地域ごとに違い、その起源もとても古いものでした。
「数年前にルールを教わり、激ハマりしたこの指遊び。いい加減ゲームの名前を知りたくなったので友人に聞いたら『分からない』とのこと。そんなことあるぅ!!??」
Twitterで話題となったこちらの投稿。
掛け声にあわせ親指をあげた数を言い当てる遊び。誰もが一度は遊んだことがあるだろうはずなのに、その名前が分からないというのです。
山陰外の出身者
「いっせーので、ですかね」
山陰出身者
「いっせーのせっていう子もいました」
長崎県出身者
「ちっちっちっちまるちっち」
街で聞くと、地域ごとに呼び方が様々あることが分かりました。一体なぜなのでしょうか?
日本の遊び文化に詳しい専門家に話を聞きました。
大阪商業大学 アミューズメント産業研究所 高橋浩徳研究員
「物が残らないゲームについては、もう年代はほとんどわからない。そのくらい古い」
まずはこの遊びの起源について。
高橋さんは、互いに右手の指を屈伸して出し、伸ばした指の合計をいい当てる遊び「本拳」が起源ではないかとのこと。
大阪商業大学 アミューズメント産業研究所 高橋浩徳研究員
「傾城真之心といういわゆる庶民向けの小説の挿絵に、人間が本拳をやっているところの絵が描かれている」
中国から伝わったと考えられていて、日本への正確な伝来時期はわからないものの、江戸時代の絵に描かれていることから、このころには市民の間に浸透していたと考えられるとのこと。
そして、地域ごとに様々な呼び方があることについては…。
大阪商業大学 アミューズメント産業研究所 高橋浩徳研究員
「いち、にの、さん、みたいなタイミングを合わせる言葉ですので、もうなんでもいいわけですよね」
それぞれの地域、コミュニティの中で独自にタイミングを合わせる言葉を生み出し遊んでいたことが、様々な呼び方や掛け声が存在する理由だといいます。
大阪商業大学 アミューズメント産業研究所 高橋浩徳研究員
「新聞や雑誌やテレビ、ラジオがない時代は、人間のコミュニティの範囲というのは自分が住んでいる範囲だけですから、地域の数だけものの名前があったわけですよね」
ところで、街で多く聞かれたのが…。
街の人
「指スマ1とか」
街の人
「指スマで育ったのでそれ以外はわかんないかも」
「指スマ」という名前です。
大阪商業大学 アミューズメント産業研究所 高橋浩徳研究員
「多分名前が特に決まっていなかったので、指を使うゲームでSMAP×SMAPでやるんだからということで『指スマ』という名前を考えついたんだろうと思います」
1996年から放送されていた全国放送のテレビ番組「SMAP×SMAP」。
番組内でこの遊びが行われていて、それが広まり全国で定着していったのではとのこと。
高橋さんによると、メディアの発達により情報が広く伝わるようになった分、ものの名前が自然と統一されていき、地域で違うということが昔に比べ少なくなっているということです。