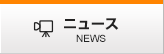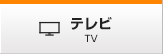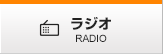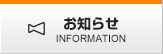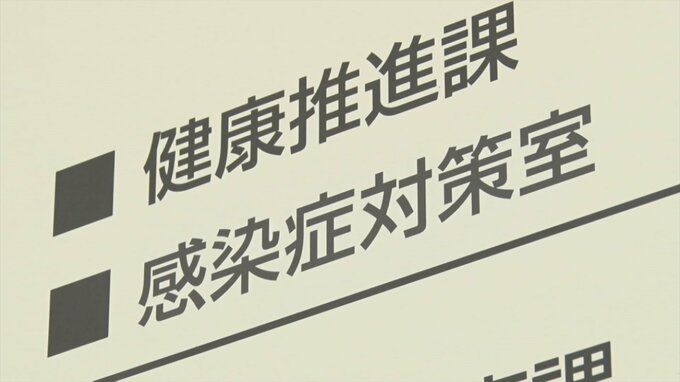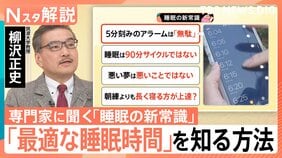島根県では、9月13日時点で約4000人の自宅療養者がいますが、病床使用率は20%台となっていて、一見余裕を残しているように見えます。
しかし第7波の医療のひっ迫はまだ続いていると、感染症対策のトップは訴えます。
島根県感染症対策室 田原研司 室長
「今、3割程度のベッドの使用率なんですが、7割余っている、この7割は余裕のある数字ではないです」
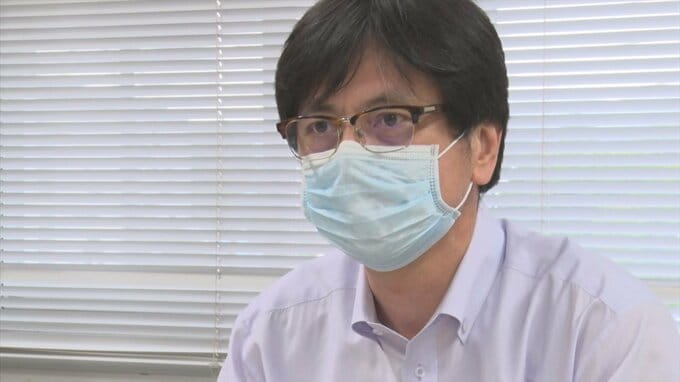
島根県感染症対策室の田原研司室長は、それでもまだ「余裕がない」状態だと言います。7割以上も空いているのに、なぜなのでしょうか?
島根県感染症対策室 田原研司 室長
「病院の中でのクラスターが多数発生しているのが第7波の特徴です。クラスターが発生すると、病棟、診療科を一旦止めるということも各病院されています。そうするとコロナ医療にも影響があるというのが事実です」
第7波で医療提供側にも感染が広がっているうえ、コロナ病棟の入院患者の9割が高齢者であることも影響していると言います。

島根県感染症対策室 田原研司 室長
「介護度が高い方認知症の人がおられたりすると、患者さん1人にかかる医療スタッフの数が2倍3倍とかかります」
第7波では、患者1人に必要な医療スタッフの人数がこれまでよりも数倍も必要なため、ベッド自体は空いていても、マンパワーの面でのひっ迫が続いている状況なのです。
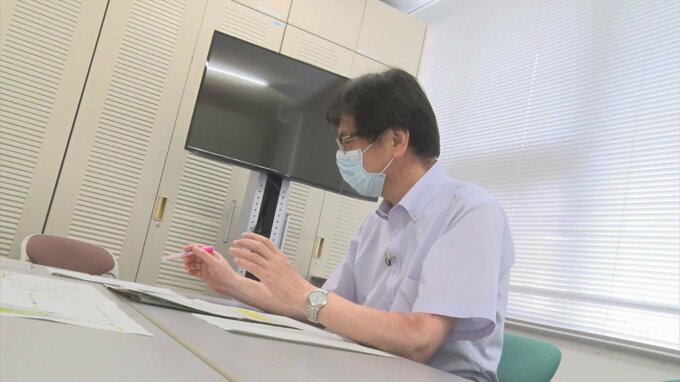
島根県感染症対策室 田原研司 室長
「医療の崩壊を起こさない。一番最後の砦が医療機関。ここをどう確保し、守るかだと思っています」
島根県内では、いわゆる「重症化リスク」が高いとされる人でも、検査時点で軽症なら自宅療養となる状況で、まだまだ予断を許さない状況が続いています。