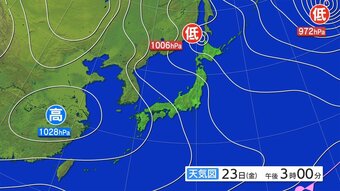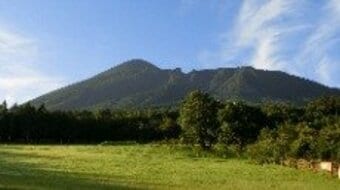一方こちらは、同じ日に行われた、岩手県宮古市での津波避難訓練です。
宮古市のNPO法人「津波太郎」が企画したもので、宮古市田老の高台に震災後設けられた公園を会場に、炊き出しなどが行われました。
徐々に辺りが暗くなるなか、公園に隣接する公民館で行われたのは、ドローン操作の体験会です。
住民に操作を教えるのは、県立大学宮古短期大学部のドローンサークルのメンバーです。このドローンサークルは去年4月に結成され、市内各地の避難訓練に参加して行方不明者の捜索を想定した飛行を行うなど、空からの防災・減災への貢献を目指しています。
現在のメンバーはおよそ30人。今年加入した1年生の中には、地元・宮古市田老出身の学生もいます。
(宮短ドローンサークル 遠藤隼さん)
「(ドローンは)災害時に役立つように今なってきているので、自分も飛ばせるようになって、地元とかほかの地域に貢献できたらいいなって思います」
各地で進む防災へのデジタル技術の活用ですが、県の復興防災DX研究会の座長を務める県立大学の杉安和也講師は、導入には慎重な検討も必要と指摘します。
(県立大学総合政策学部 杉安和也講師)
「いわゆるデジタルトランスフォーメーションっていうキーワードが出てきているなかで、例えば明日からデジタル技術を使っていきましょうって思ったとして、それがいきなり実現できるかというと、実はそうではないのが現実だと思うんですね。それぞれの実情に応じて導入ができる部分を段階的に考えていくってことでいいのではないかと思っています」
デジタルのインフラ整備にかかる費用の問題や、万が一災害が発生した場合に自治体や住民が最新技術を使いこなすことができるのかなど、デジタル技術の活用の浸透には不透明な部分が多いのも事実です。
災害時に多くの人の命を救うことが期待される技術のメリットとデメリットを比較しながら、活用の模索が続きます。
注目の記事
なぜZ世代は、SNSで連絡先交換するのか「写真でどんな人か分かる」「いきなりLINE交換は驚く」「3アカウント使い分けて…」通信で変わる“人間関係”

交通事故死の8倍が“入浴中”に…富山が死亡率全国ワースト ヒートショック防ぐ「10分前暖房」「40℃」「半身浴」の鉄則

「雪で信号が見えない」長崎で目撃された現象 原因はLED化? ‟省エネ・高寿命‟が裏目に…盲点の雪トラブル

薬物の売人「最後には先輩を売った」 “クスリ一本” で暮らそうとした若者は今… 薬物依存が狂わせた人生― 3人の若者が語った闇(3)

暖房をつけても足が寒い=コールドドラフト現象 寒い家で健康被害も 対策は“空気の循環”

初代トヨタ・ソアラで「未体験ゾーン」へ、期間限定レンタカー始まる 80年代ハイソカーブーム牽引の名車、最上級グレード2800GT-Limitedの上質な走りを体感