「特定妊婦」。病気や経済的な理由で育児が困難な妊婦を指す。現行法の枠組みでは、行政が指導や助言をしてその妊婦の子育てを支えることになっている。しかし、実態はそううまくいっていない。「行政」といっても特定妊婦をサポートする専門機関があるわけではない。結局は、自治体や児童相談所などの既存機関が連携して対処することになる。専門家は、担当者の人数が足りず、この分野に明るい人材も不足していることを指摘する。それが、一応の情報共有はなされるものの、具体的な支援策まで練られないまま「事件」が起きてしまう事例につながっているという。福岡県では、行政の連携がうまくいけば救えたかもしれない命が失われた―。
◆10年で10倍に増えた「特定妊婦」
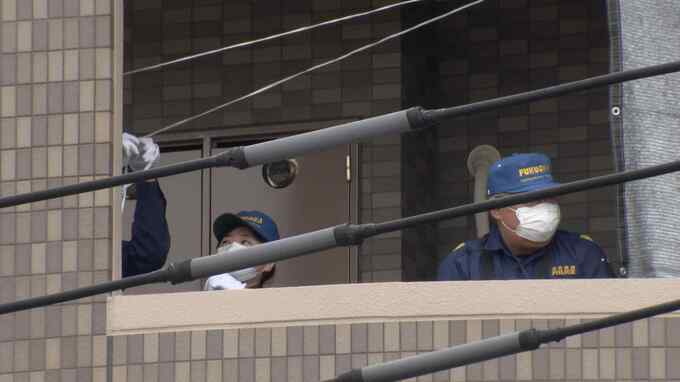
生後7か月の井上新大ちゃんは、福岡県大野城市のマンションで母親と双子の弟の3人で暮らしていた。胸などを圧迫されたことによる肝臓破裂で去年、死亡した。体には複数のあざがあった。

大野城市の会見「不適切な養育環境があった家庭であると転入前の自治体から情報提供があったため妊娠中から特に支援が必要であると認識し、児童福祉法の“特定妊婦”として、要保護児童対策地域協議会で管理支援を開始したところです。その後9月に出生されましたので、特定妊婦から2人の要保護児童がいる家庭として管理を継続していたところです」
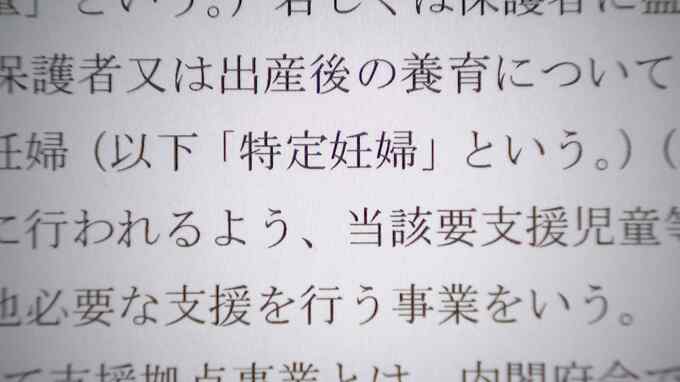
虐待を防ぐ目的で2009年に施行された改正児童福祉法。そこに「特定妊婦」という言葉が明記されている。「特定妊婦」とは、精神疾患や予期せぬ妊娠のほか、経済的な理由で育児が難しく、妊娠中から支援を必要とする妊婦のことだ。大野城市は、母親を「特定妊婦」とし、出産前から面談や電話で接触していた。新大ちゃんは「要保護児童」とされていたが、生後7か月で命を落とした。














