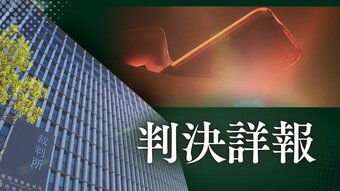◆巨大なコイルで電気を生み出す

直径2メートルほどのパイプを毎秒70トンの水が流れ、タービンを回す。水が通り抜ける「ケーシング」と呼ばれる管の中を職員が点検していた。大人がかろうじて入れるぐらいの小さな穴だ。
「0.8ミリです」「0.8ミリ了解しました」
測定した数値を側に控える別の職員に伝え、職員がメモをとる。

続いて案内されたのは、タービンとつながる「発電電動機」。原理は、同じようにタービンを使う火力発電も原子力発電と共通だ。磁石をコイルに近づけたり離したりする際の「電磁誘導」で電気を取り出す。赤く塗装された巨大な“コイル”に圧倒される。
職員「この内側一体が回転します。下から見て右に回ったら揚水する方向ですね。逆に回ったら発電します。絶縁ワニスが浮いていたりするんで補修します」
◆“揚水式”の稼働はこの10年で3倍に

九州電力(九電)の管内では、天山発電所を含め3か所の揚水式発電施設が稼働している。太陽光発電の普及に伴って昼間に余ってしまう電力を有効活用するため、揚水式発電所の稼働は10年前と比べて3倍に増えた。その分、施設にかかる負担も増えているという。

九電佐賀水力事業所・川端一伸所長「太陽光の連携が増え、昼間の揚水が盛んに行われるようになりました。未然にトラブルがないようにしたいと思っています」
電力を無駄なく使い、太陽光発電の更なる普及にも一役買う揚水式発電。点検作業は、今月12日まで続く予定。