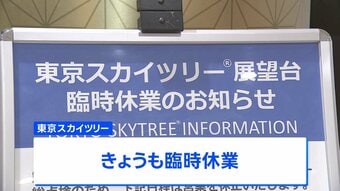秦澄美鈴(26、シバタ工業)が20年ぶりの室内日本新をマークして帰国した。2月12日にカザフスタン・アスタナで行われたアジア室内選手権女子走幅跳。秦は4回目に6m62と、03年に花岡麻帆がマークした6m57の室内日本記録を5cm更新。6回目に6m64と伸ばし、2位のファン・インイン(18、中国)に21cm差で快勝した。屋外でも日本記録の6m86(06年・池田久美子)の更新と、今年8月開催の世界陸上ブダペスト大会標準記録の6m85突破が十分期待できる内容だった。
今季目指す助走ができたアジア室内選手権
23年初戦となったアジア室内選手権。秦に「室内日本新も頭の片隅にあった」ことは事実だが、そこまで仕上げて臨んだ試合ではなかった。
冬期練習中は、屋外シーズン(おおよそ4~10月)ほどスピードを上げていない。1回目はかなり慎重な跳躍だったという。
「初戦で、どのくらい跳べるかわかりませんでした。(ファウルしないで)記録を残しに行こう、と跳んだ跳躍でした」
それでも6m51と、1回目の試技としては自己最高記録を跳んだ。結果的に2位の中国選手は、秦の1回目の記録を上回ることができなかった。そのくらいアジア室内選手権の秦は強さを見せていた。
メンタル的にも、昨年の世界陸上オレゴンを経験したことで「海外試合だからといって、そわそわした感じはあまりなかった」という。自分の跳躍をすることに集中できていた。
助走開始位置を調整した2回目はファウル、元に戻した3回目は6m54。そして4回目に6m62と室内日本記録を更新した。
「1~3回目の間に、(今季の走り方として意識していた)どんどん前に進んで行く走りをして、それがハマってきました。ストライドを伸ばすというより、お腹のあたりを引っ張られるような走りです。昨年までは踏み切り前で詰まる(小さな歩幅で脚の回転を速くしたり、窮屈そうな脚さばきになったりする)助走をしていました。最後も(感覚的に)加速しながら、 “詰まらず”に大きな走りで踏み切りに移行することが理想ですが、アジア室内選手権はそこに近づいたと思います。その日のベストの跳躍はできました」
5回目は6m46と記録を下げてしまった。踏み切りの「タタン」というリズムを強調しすぎて、ブレーキが大きくなった。6m64と室内日本記録を2cm更新した6回目は、「ほどよく前に抜けた跳び出し」ができた。昨年は「前に抜けても高さが出ていた」が、アジア室内選手権は前方へ跳び出す勢いが大きい踏み切りになった。大きく走る助走は、その踏み切りをするための助走でもあった。
陸連科学委員会からのアドバイスと世界陸上の経験
昨年の秦は20歩助走で、風など条件によって微調整はするが、40mの助走距離をベースにしていた。それをアジア室内選手権では「大きく走る」助走に変えたことで、40m80cmをベースに試技を行った。
変更に踏み切ったのは、昨シーズン後に陸連が行った「フィードバック合宿」(秦)で指摘されたことがきっかけだった。
「兵庫リレーカーニバル(22年4月)の1本目の跳躍は6m40だったのですが、実測値は6m76でした。1本目ではよくあるのですが踏切板に合わず、10cmくらい手前から踏み切ったんです。助走の終盤で『(踏切板が)遠いわー』と感じて、ピッチを速くするのでなく、大きな走りで少しでも板に合わせようと踏み切りに入っていきました。自分では失敗助走と感じていたのですが、科学委員会の方からも、強化コーチからも、『この助走をやってみれば』とアドバイスされたんです」。
そのアドバイスを素直に受け容れられたのは、世界陸上で外国勢を間近に見たことが背景にあった。
「生で海外のトップ選手を見ましたが、踏み切り前に脚を(速いピッチで)回している選手はいませんでした。助走の流れ的にも、最後に詰まって跳んでいる選手はいなかったんです」
外国勢と自身の違いが、そのときから秦の脳裏に刻まれていた。陸連合宿を経て「やってみる価値はある。23年はその走り方に挑戦してみよう」と助走の変更を決意した。
やってみると前述のように、踏み切った後の前方への勢いが強くなった。
「昨年までは短い距離の中で脚を回すので、コントロールができなかったとわかりました。大きな走りに変えた後は、駆け込みながら“突っ込んで行く”感じの踏み切りができるようになったんです」
冬期で助走スピードが上がっていないなかでも室内日本記録を出すことができたのは、助走の変更で踏み切りを変えることができたからだった。