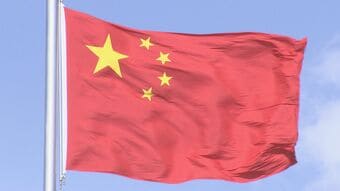■師走到来 “寒さの歴史”に思いを馳せると…
師匠も走り回る12月、寒さもいよいよ本格化してきましたね。あ~寒い。密閉率も断熱性も高い現代のマンションに住んでるのに、なんでこんなに毎日寒いんだろう?ふと考えるわたし。頑丈なコンクリートと厚いガラスでも寒いのに、平安時代は扉も壁もほとんどない、寝殿造りで貴族たちは寒さをしのげていたのでしょうか?
そんな心配は無用でした。いや、無用というほどではないですが、平安時代は少なくとも今ほど寒くはなかったようです。
日本の宮中におけるお花見の宴は嵯峨天皇の812年に始まっているそうなのですが、9~10世紀の宴の日付は平均で4月10日。今の京都の桜の満開日に比較すると6日早く、今より温暖だったことが推定されます。

皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、歴史を振り返ると地球は寒冷期と温暖期を周期的に繰り返しています。周期的といっても、かなり長い周期です。
例えば、太陽を回る地球軌道のわずかなずれによって生じる氷期と間氷期は、約10万年の周期で起こっています。もう少し最近に注目すると、ここ2000年でも地球全体ではないものの、小規模な気候変動があったことが分かっています。
代表的なのが「中世の温暖期」(日本では8世紀~12世紀頃)や「小氷期」(14世紀~19世紀半ば頃)と呼ばれるもので、これには太陽活動の強弱や火山の噴火が深く関わっているそうです。平安時代はちょうど、その中世の温暖期にあたる時期だったのです。
中世の温暖期というと、ヴァイキングがグリーンランドに上陸したことがよく知られています。そのヴァイキングの勢いは、中世温暖期に拡大しています。理由は諸説ありますが、温暖な気候により北方の海が凍結しなくなり、遠方への航海が可能になったことが後押ししただろうことは容易に想像できます。
もっと短い期間の異常気象でさえ、歴史に大きな影響を与えています。
1780年代はアイスランドなどで火山が大噴火を起こし、世界各地で異常気象が発生しました。1788年~89年はヨーロッパ全土で厳しい冬となり、フランスではおもな河川が凍結し、商業活動がほとんど停止。春になると雪解け水が農地に氾濫しました。
1789年~1799年の間にはフランス革命が起こっていますが、革命の起きた1年と1日前には直径12センチほどの大きな雹がフランスを襲い、農作物が大打撃を受けていました。最大の要因とはいえないものの、気象が与えた影響は少なくなかったことでしょう。
こんな風に、時代の変革期には気象が関わっていることが多くあります。