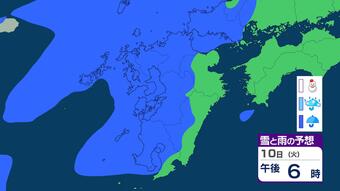夏休みが終わり、新学期が始まった今週。しかし、楽しいはずの学校生活に息苦しさを感じている子どもたちがいます。長崎県内の不登校児童・生徒は過去10年で2.5倍に増加し、昨年は統計開始以来最多を記録しました。その背景には何があるのでしょうか?そして、子どもたちの孤立を防ぐために広がる新たな「居場所」の支援とは?多様化する不登校の現状と対策に迫ります。

県教育庁児童生徒支援課 大野洋平係長「一番注意しなければならないのは夏休み明けとか」
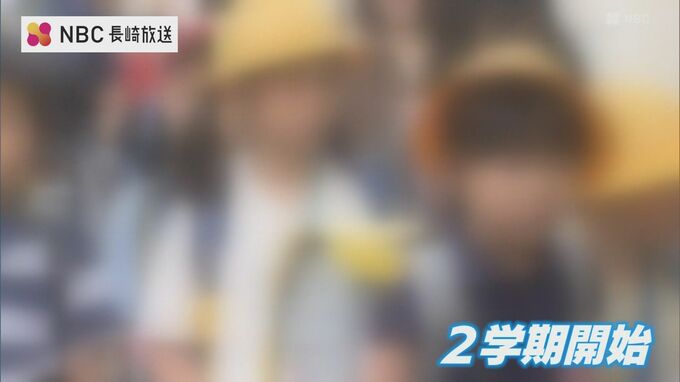
夏休みが終わり2学期が始まった今週。音楽会や運動会、修学旅行など、楽しみな行事も目白押しですが…
大野係長「ちょっとエネルギーが枯渇して不登校になりがちな時期というのは《長期休業明け》というのがあると思います」

長崎県内における過去10年間の不登校の児童・生徒数の推移をみると、8年連続で増加していて、2023年度は統計開始以降最多の4,095人。10年で2.5倍に増えています。全国的にもいま増加傾向にある不登校。背景には何があるのでしょうか?
県内の現状・増加の背景は
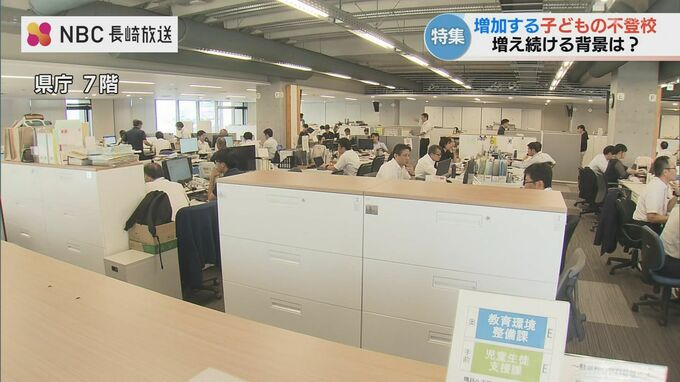
不登校支援や教育相談などに対応している県の児童生徒支援課です。8年連続で増えている不登校者数。増加の背景には大きく2つの要素が考えられると言います。

大野係長「教育機会確保法というのが平成28年にできて、それによって子どもたちが休養をとることの重要性であるとか、登校することだけが不登校支援の目標じゃないとか、そういったことも言われるようになって、だんだん社会の認識がそのように変わっていったっていうのがまず一つ。
もう一つが新型コロナがあったことで学校登校が制限されたり子どもたちのコミュニケーション、そういった機会が少なくなってしまったり、登校が制限されている時間に家庭で過ごしていて、生活が乱れてしまって、そのまま不登校になるといったケースも報告がされております」
不登校の理由は子どもによって様々で──
・学校での人間関係や家庭での親子関係が引き金となるケース
・生活リズムの不調
・不安
・抑うつなども挙げられます。
大野係長「誰にでも起こり得る。子どもたちの不登校自体が問題というわけではなくてですね。それによって子どもたちが学ぶ機会がなくなったりとか、社会から隔離されたというか分離されたような状況が長く続くということは避けたいなと思っているところです」

不登校増加の背景には「つらいときは無理に学校に行かなくても大丈夫」という考え方の広まりや、新型コロナウイルスの影響も不登校の増加に拍車をかけたと分析されています。一方、休むこと自体が問題なのではなく、その期間に人と社会との接触機会が失われることが懸念されています。