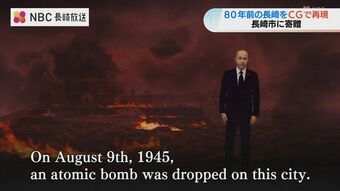世代を超えて被害が続いている可能性が指摘されている、半世紀前の食中毒「カネミ油症」。被害者の子どもや孫に高い発生傾向があると報告されていた口唇・口蓋裂について、全国油症治療研究班は報告件数を訂正した上で「現時点で関連があるとは言い難い」とする見解を示しました。
13日に福岡市で開かれた「油症対策委員会」。油症患者の治療法などを研究している全国油症治療研究班が、年2回患者に最新の研究を報告する場です。
2021年から進められている次世代調査には、これまで油症認定患者の子と孫あわせて443人が参加しており、研究班が「先天性の口唇・口蓋裂の発生率が高い傾向にある」との見解を示していたことから、次世代救済の足掛かりになることが期待されていました。
しかし13日の会合で中原剛士班長は、口唇・口蓋裂を訴えた3人を再調査した結果、2人に症状がないことが判明したとして「現時点で油症と関連があるとは言い難い」との見解を示しました。
口唇・口蓋裂ではなかった2人については、調査票への誤記載だったとしています。
説明を受けた患者からは「口唇・口蓋裂で既に亡くなった人もたくさんいる」などの声が上がり、研究班は今後、治療痕などの確認も含めて調査を継続する考えを示しています。
汚染油を食べた被害者から生まれた子どもには、胎盤やへその緒を通して、原因物質であるPCBやダイオキシン類が移行したケースが確認されています。被害者からは「直接油を食べた被害者から生まれた子どもに症状がある場合は、患者に認定して治療費を補償してほしい」といった声や「3人の子ども全員に症状があり、医療費が生活を圧迫している。親として責任を感じる」などの声も上がりました。