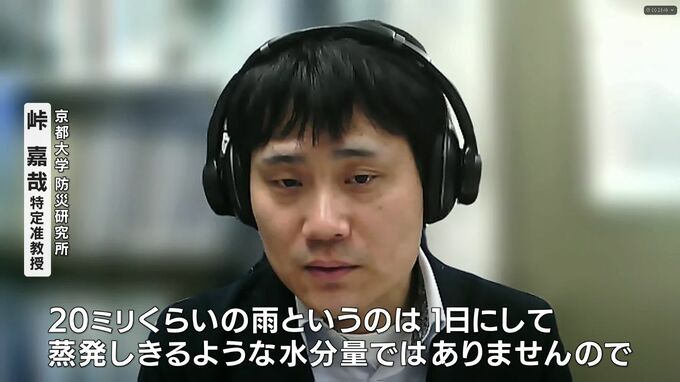岡山県岡山市南部の山林火災は岡山県内で過去最大の焼損面積となっています。なぜこれほどまでに延焼が拡大しているのでしょうか。要因と今後の見通しを専門家に聞きました。
(京都大学防災研究所 峠嘉哉特定准教授)
「林野火災はひとたび大きくなってしまうと、たちまちのうちに消火してしまうというのは非常に難しくて、燃焼の範囲が広いですから、すべての範囲を消防力によってたちまち消すというのは非常に難しいわけです」
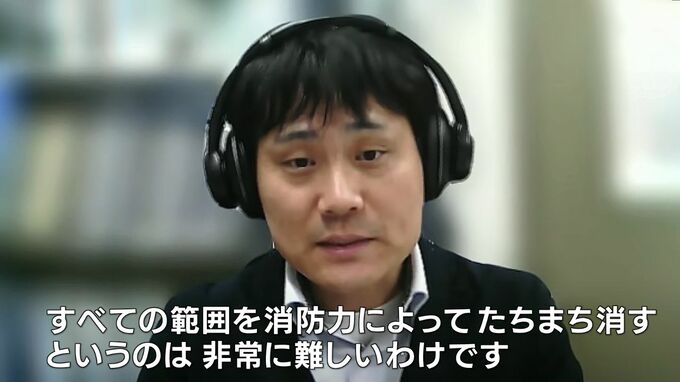
話を聞いたのは、京都大学防災研究所の特定准教授、峠嘉哉さんです。今回の山林火災はなぜこれほどまでに延焼が拡大しているのか。峠さんはここ数か月、雨があまり降らなかったことと、西日本に多い真砂土の地質を要因にあげます。
(京都大学防災研究所 峠嘉哉特定准教授)
「岡山県でいえば12月から2月までの3か月間の降水量が平年の20~30%くらいしかない状態、加えて真砂土というのは砂質成分が多いものです。それは結局雨が降った後にスッと抜けてしまう感じで、なかなか水分をキープしてくれないですので延焼速度が早く、大きくなってしまったということがあろうかと思います」

そして、強風などの条件も重なり今回の火災では、ある現象が起きているのではと話します。
(京都大学防災研究所 峠嘉哉特定准教授)
「葉っぱから葉っぱに延焼するような形態、これが樹冠火と申しまして、樹冠火に至ると延焼速度が速くなる。また、飛び火が増えるといったことが知られています。今回でいうと、1日にして100ヘクタール、200ヘクタール大きくなった事例と伺っていますので、その延焼速度の速さを考えますと、樹冠火が起こったのではないかと考えています」

今夜は、岡山県南部では10ミリから20ミリほどの雨が予想されています。今後の見通しについて峠さんは・・・
(京都大学防災研究所 峠嘉哉特定准教授)
「20ミリくらいの雨というのは1日にして蒸発しきるような水分量ではありませんので、今燃えている所だけじゃなくてこれから燃えようとするところも、予備的に湿潤にしてくれる。ですから、これから林野火災が広がるということに対してはある程度鎮静化することが期待できる」