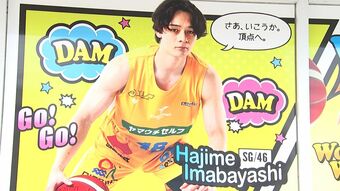東日本大震災の発生からきょう(11日)で14年です。災害時に弱い立場におかれがちなのが、高齢者、障がい者など一般に「災害弱者」と呼ばれる人たちです。一人で避難生活を送ることが困難な場合が多く東日本大震災では災害関連死で亡くなった方の実に90%近くが66歳以上の高齢者だったというデータもあります。こうした人たちを守ろうと、岡山・香川の各地には介護設備が整った障害者施設・老人ホームなどを「福祉避難所」に指定しています。ただ、取材を進めるとこの「福祉避難所」を巡った大きな課題が見えてきました。
福祉避難所の現実

多くの介護職員たちが組み立てているのは、非常用のダンボールベッド。2月、美咲町の老人ホームで開かれていたのは職員向けの防災講習会です。防災士から災害や避難方法に関する講義を受け、また救命方法や発電機など災害備蓄品の使い方も学びました。

(職員)「寝れる寝れる、2人で寝れる」
ここは「福祉避難所」に指定された老人ホーム。福祉避難所とは、高齢者や障がい者など、支援が必要な被災者が避難生活を送るための施設です。災害時に避難所として活用することになっています。
Q「いざというときは設備使えそうですか?」
(職員)
「大丈夫だと思います。何かあったときは自分が一番に積極的に行動できるように今日学んだことを発揮できるようにしたい」
職員からは「勉強になった」との声が聞かれる一方で、施設を運営する松本博之さんは頭を悩ませていました。