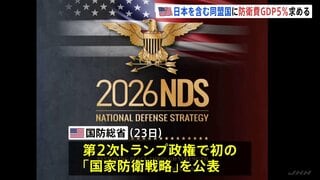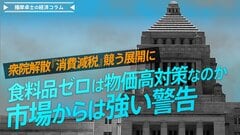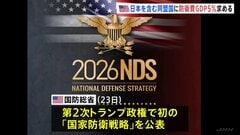新政権の最初の関門は「閣僚承認」
2025年1月20日、米国ではトランプ新政権が発足する。米国大統領の返り咲きはクリーブランド氏以来132年振りとなる。就任前からトランプ氏のSNS上での情報発信が話題となるなど、一次政権と同様、各国要人や金融市場はその予測不能な行動に振り回されそうだ。
しかし、「世界最高の権力者」と呼ばれる米国の大統領であっても、自身の主張を完全に政策へと反映できるわけではない。大統領には法案作成や予算策定の権限はなく、これらを担うのは立法府である連邦議会だ。議会がトランプ新大統領の主張をどれだけ受け入れるのかが、トランプ2.0の方向性を占う焦点となる。
この点において、トランプ新大統領の最初の関門は閣僚人事の承認だ。人事を承認する上院では共和党が過半数を占めるものの、トランプ氏と距離を保つ穏健派が一定数いるとみられている。賛否両論のある候補者たちの承認プロセスがすんなり進まないとなると、過激な政策スタンスは現実路線へとシフトする可能性がある。
本稿執筆(1月8日)時点において、新政権の顔には「アメリカ・ファースト」と「トランプ・ファースト」を体現する人物が並ぶ。例えば、外交を担う国務長官には対中強硬派のルビオ上院議員、通商交渉などの産業政策を担う商務長官には関税を称賛するラトニック氏(投資銀行経営者)が指名された。一方、国防長官候補のヘグセス氏はトランプ氏への忠誠心が評価されたとみられるが、元テレビ司会者でその資質には疑問の声が挙がる。また、医療政策を担う厚生長官に指名されたケネディ・ジュニア氏も、反ワクチン活動家であり承認への不透明感が残る。
減税策と関税策の行方
新政権が閣僚人事でつまずく場合、その後の注目点である減税政策はより小粒な規模に留まるかもしれない。トランプ氏は選挙戦において、2025年末に失効する家計向け減税等(所謂「トランプ減税」)の延長に加えて、チップ収入や残業代に対する免税など、広範な減税策を主張した。
こうした公約を実現するためには今後10年間で10.4兆ドル(約1,600兆円)の膨大な財源が必要となる(超党派の責任ある連邦予算委員会の試算)。一方、財政悪化を懸念する一部の共和党議員がこれに全面的に賛成する可能性は低く、トランプ氏による議会への影響力が実際の減税規模を左右する。具体的には新政権が春頃までに公表する予算教書、夏から秋頃にかけての議会審議の行方が注目されよう。
また、財源論を巡っては起業家のイーロン・マスク氏の動きも焦点だ。同氏らが率いる「政府効率化省(DOGE)」は、政府支出の無駄を削減することで年間5,000億ドル(約80兆円)を賄えると主張する一方、サマーズ元財務長官は「馬鹿げたアイデア」と一蹴するなど、懐疑的な声も少なくない。
一方、議会の意向を気にせず、トランプ氏自身の裁量で動かしやすい政策もある。その代表例は関税政策だ。2024年11月、トランプ氏は移民対策等を理由に就任日に対中関税を10%、対カナダ・メキシコ関税を25%引き上げる方針を示した。関税政策はあくまで「脅しの道具」に過ぎないとの見方は根強いが、トランプ新大統領がこうした楽観的な予想を裏切ってくるリスクに警戒が必要だ。
11月に表明した関税対象には米国の同盟国であるカナダが含まれており、「トランプ暴走シナリオ」では日本の対米輸出にも高関税が課され、輸出の急減と景気の大幅な悪化を招く可能性が高まる。日本が高関税を避けるためには、米国からの農産品や防衛装備品の輸入拡大、及び自動車産業を中心とした投資拡大による米国での雇用拡大などが求められるだろう。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 主任エコノミスト 前田 和馬)