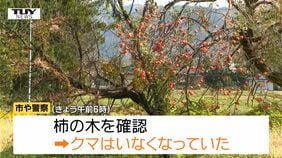富士山噴火の避難計画が改定され、住民は原則、徒歩避難とされました。各自治体が今後、具体的な計画を策定することになります。
長崎知事:
行政からの一方的な情報発信だけではなく住民との対話などに時間をかけ官民が一体となり、「逃げ遅れゼロ」の達成を目指す。
清水祐甫記者:
噴火の兆候が表れたとき自治体には観光客や一般住民が混乱しないような対応が求められます。
年間およそ500万人もの観光客が訪れる富士河口湖町です。噴火警戒レベルが3になった時点で帰宅を促すことになりますが…
観光客は:
「大渋滞が起きた時にどうやって帰るか」
「車で避難できればするが、たぶん混雑する。逃げ切れなくなってしまう」
住民も慌てて避難することが想定され、大規模な渋滞が発生するおそれがあります。そのため原則、徒歩避難となっている住民への周知がカギとなりそうです。
富士河口湖町 地域防災課 渡辺大介防災係長:
すぐに御坂峠を越えて甲府方面に避難しなければというイメージが刷り込まれていたかと思うが、慌ててすぐに遠くまで避難するのではなく冷静に正確な行動をとっていただきたい。
ただ富士山では火口の位置を噴火の前に特定することは困難なため、住民がどこに避難するかは避難計画の中で定めていません。
富士河口湖町 地域防災課 渡辺大介防災係長:
富士山の噴火の状況に応じて避難所を開設するので、火口が定まっていない状況の中で、ここに避難してくださいと あらかじめ決めておくのは危険性があるので、その時の状況を冷静に判断して落ち着いて行動しいただきたい。
町はほかの市町村への避難も含め臨機応変に避難先を確保するとしていますが、自治体同士の連携など素早い体制整備が求められます。