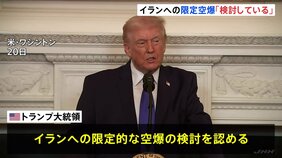やまがたStep!のコーナーです。
山形県酒田市の木工店が取り組む「船箪笥」作り。
今回は、ある技術を生かした三作目の製作現場にカメラが密着しました。
港町の伝統をつないでいこうする職人の思いに迫ります。
木工店が江戸時代のつくり方で再現する「船箪笥」

山形県酒田市にある木工店、加藤木工です。
木工製品を手掛けるほか、家具の修理を行っています。
ここで、先月始まったのが、「船箪笥(ふなだんす)」作りです。

加藤木工・加藤渉さん「より江戸時代に酒田で船箪笥が作られていた当時の作り方で再現したいと思ったので」
そもそも船箪笥とは。

船箪笥が生まれたのは、北前船の舟運文化が盛んだった江戸時代。
船に乗る商人たちが、お金など大事なものを保管していました。
そのため、一般的な箪笥よりも頑丈で、持ち運びやすい大きさに。
かつて、多くの北前船が往来していた港町・酒田でも、船箪笥が盛んに作られていました。
しかし、時代の変化のなかで、今では、船箪笥はほとんど見ることがなくなってしまいました。
そこで立ち上がったのが、加藤木工の加藤渉さんです。

加藤木工・加藤渉さん「我が家はずっと指物、木工業を続けていたが、そういった企業がだいぶ減ってきている。でも、酒田は昔、木工業や建具が盛んであったと言われている。そういったことを伝えていくためにも、フラッグシップというか旗艦の作品として、船箪笥を作り続けていくことが加藤木工のあるべき姿かなと思っていまは挑戦している」

加藤さんは、地元の伝統を後世につないでいきたいと、
おととし、父・治さんと、およそ30年振りに船箪笥を復活させました。
そして三作目となる船箪笥作り。今回はある技法に注目しました。
加藤渉さん「酒田の船箪笥の真骨頂は、蟻組(ありぐみ)だと言われています」