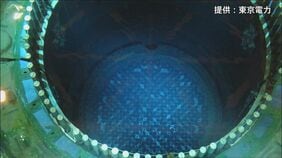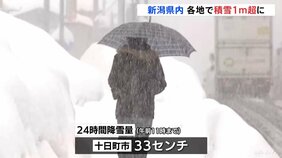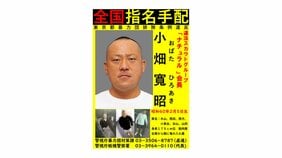今年も雨のシーズンが近づいています。去年7月の大雨を教訓に、災害に強い県づくりを目指すための会議が、きょう県庁で初めて開かれました。
会議では、災害を経験した市町村がどんな課題を感じたかが共有されました。

この会議は、去年1月の能登半島地震や去年7月をはじめ県内をたびたび襲った大雨災害を教訓に、今後の災害対策を考えるために、県が初めて開きました。
会議には、過去に災害対応を経験した市町村や防災教育を行う学校関係者、災害を研究する大学の教員などの有識者が参加しました。
初開催となったきょうは、最初に去年7月の大雨災害の振り返りを行い、河川のはん濫などの影響で災害救助法が適用された県内16の市町村に対して行った、県のアンケート調査の結果が報告されました。

それによりますと、災害が起きた場合の初動対応や、復旧・復興に向けた対応についてはほとんどの自治体が課題を感じなかった一方で、浸水した家から出される家財道具などの災害廃棄物への対応や、災害ボランティアセンターの設置・運営を含む応急対応については、回答した自治体の半数以上が、何らかの課題があったと答えました。

このうち、災害廃棄物を集積所へ運ぶことのできない人への対応や、災害ボランティアセンターの運営に関わる人の数とノウハウの不足など、さまざまな課題があげられたということです。
この会議は今後も定期的に開かれ、県は会議を通じて有識者の意見を参考にしながら報告書をまとめ、緊急に取り組むべきと判断された施策があった場合は、来年度の予算に反映するということです。