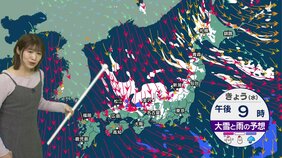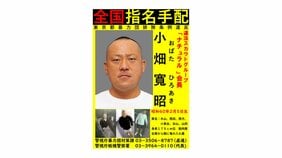8月、愛媛の高校生や大学生たちが、東北の被災地を見て回るスタディーツアーが行われました。薄れゆく震災の記憶を次の世代に引き継ごうと、福島から愛媛に避難した人たちが、企画しました。1000キロ以上離れた愛媛の若者たちに、被災地はどう映ったのでしょうか。
8月11日、福島県南相馬市小高区の閉校した小学校で、話を聞く若者たちがいました。同じ場所には幼稚園もありました。

当時、園長だった女性が震災直後の状況を伝えます。
当時園長だった女性「夜中に消防の人が来て、外どうなっているのと聞いたら、一歩も出れない大変なことになっていると。死体が浮かんでいて…」
渡部寛志さん「ここ景色見ると、ちょうどあそこに低い山があって、海が見えないでしょ。海が見えないけど、実は田んぼが広がっていて…ここは福浦というところで、大正時代に海を干拓したところ」

一緒に説明をするのは、渡部寛志さんです。今回のツアーを企画した一人で、原発事故の後、愛媛と小高を行き来しながら、農業を営んでいます。
実際に被災地を歩き、経験した人の話を聞いてもらうことで、震災や原発事故を知らない世代に、記憶や教訓を引き継ぐ。そんな思いで、このプロジェクトが始まりました。
松山学院高校・小林桜帆さん「いま3.11って何?って聞かれることも多くてそういうのを聞かれたときに、この子たちって知らないんだって、びっくりして…これは何か活動しなきゃなと思って(参加した)」
翌日、一行は朝から、浪江町の震災遺構請戸小学校を訪れました。これに先立ち、岩手や宮城でも被災地を見学してきた若者たち。ここ浪江でも改めて、津波のすさまじさを実感しました。

参加者「急にあんなところまで逃げろと言われても…」
参加者「走って行ける距離だとは思えんな…」
校舎の外で、請戸小学校の児童たちが避難した大平山を眺める生徒たちがいました。松山学院高校の生徒会のメンバーです。児童たちが逃げたおよそ2キロの道のりを想像します。
松山学院高校・笹園翼さん「教室だったりがもう、部屋ごとぐちゃぐちゃになるくらいで…どれだけの津波が来たのかがよくわかります」