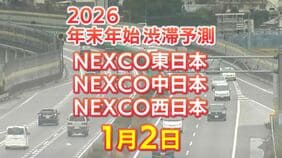深刻な不漁が続くサンマについて、日本や中国、ロシアなど9つの国と地域は、漁獲枠を25パーセント削減することで合意しました。全国有数の水揚げ量を誇る宮城県女川町では、「削減」を評価する一方で、その効果には疑問の声も聞かれます。
日本や中国、ロシアなどがサンマの資源管理を話し合う国際会議では、参加する国と地域全体での年間の漁獲枠を、去年より▼25パーセント削減することで合意しました。2021年、▼40パーセントの削減を決めて以来の規制強化です。

日本でのサンマの水揚げ量は4年連続で過去最低を更新し、女川港では、2018年の▼1万5505トンに対し、去年は10分の1以下となる▼1295トンにまで激減しました。

女川町の漁業関係者は、今回の合意を評価する一方、その効果に疑問の声を上げています。
女川魚市場 丹野秀之 専務:
「どれだけの効果があるか分からないが、資源管理をする上での第一歩。ここ数年、女川でも10分の1ぐらいの漁獲量なので、船の方も大変」
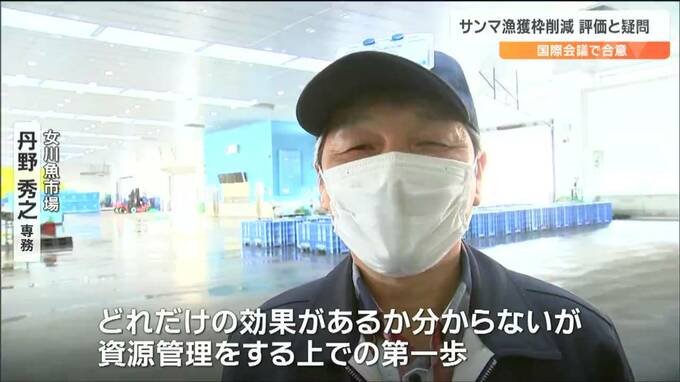
女川町の鮮魚店店主:
「大した影響はないのでは。今の水揚げ高では25パーセント減っても大した影響はないと思う。(各国の合意は)良いと思う。それだけ資源が増えることにつながる」
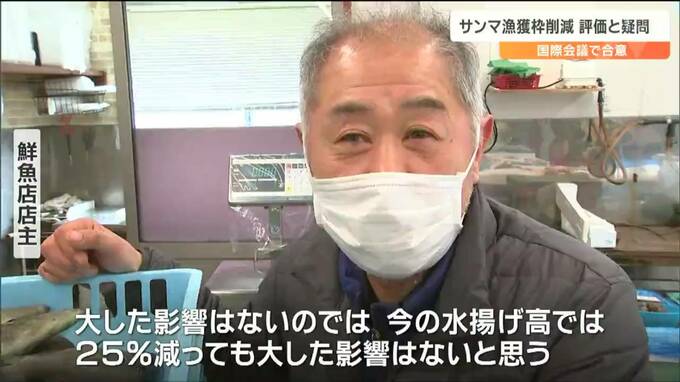
今回の合意で総漁獲枠は▼25万トン以内となりますが、去年の実績は▼9万2000トン程度にとどまっていて、実際に操業制限につながる可能性は低く、実効性には課題が残ります。