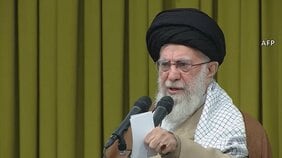宮城県多賀城市市川の「多賀城跡」で新たに発掘されたのは、南北約10m分の材木塀と大溝の遺構です。

平安時代のものとみられています。

材木塀は一本あたりの高さが当時は3メートルほどあり国府・多賀城で城の内側と外側を分ける役割を果たしていたということです。

これまでに見つかっているものと合わせると南北に250mに渡って木材の塀や溝が築かれていたことになります。

多賀城遺跡調査研究所 廣谷和也研究員
「今回見つかったのは平安時代のものなんですけれども、出入口の西北門でさまざまな工夫をしながら高低差がある地形のところに外郭施設をつくっていたことがわかったのが大きな成果」

佐藤綾香記者
「見つかったのは材木塀や大溝だけではありません。さまざまな模様のかわらも見つかりました」

1969年から始まった多賀城跡の発掘調査は5年ごとに計画を作りながら続けられています。

直近5年では、主に多賀城跡西側の外周りを中心に発掘を進めています。