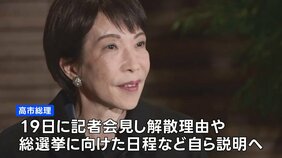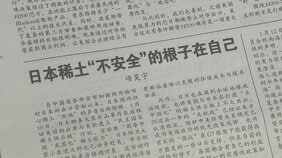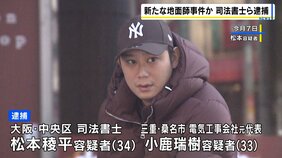高校の体育の授業や部活動の現場でAI=人工知能などを活用した取り組みが加速しています。静岡県教育委員会は「指導者不足」など現場の課題を解消できると期待を寄せています。
部活動が盛んな飛龍高校の体育の授業です。15日から新しいアプリの導入が始まりました。
立ち幅跳びをした生徒の映像に、手や足の動きと同じ点と線が現れます。
<スプライザ 豊嶋果以さん>
「スプライザモーションは、カメラ1台で動作解析ができるアプリです。マーカーなど付けなくてもカメラで撮影し、映像をアプリに入れれば、動きの角度・速度などが簡単に定量化(数値化)できます」
飛龍高校では、2025年度から「総合スポーツコース」の一部のクラスで試験的に導入しました。
<飛龍高校の生徒>
「動画を撮って、こういうのを使ってみないと細かい違いが分からないので結構便利。使いやすい」
<飛龍高校の生徒>
「正確な数値が出るので、どう変えればいいかという改善点が見つかりやすい」
学校側は生徒の学習姿勢にも変化が起きると期待しています。
<飛龍高校 板垣耕太体育主任>
「ただスポーツをするのではなくて、自分自身の運動に関する分野で自分自身を探求していくという、そういう授業なので、本当にこれまでの体育とはまた違ってくるのかなとは思ってます」
一方、静岡県松崎町の松崎高校では、県教育委員会が、スポーツ練習アプリによる部活動の支援を始めました。
アプリの中に筑波大学の学生の練習動画が入っていて、部員8人が、手本の動きを参考にしながらウォーミングアップ。お互いの動きをスマホで撮影し、手本との違いを、骨格の動きとともにチェックします。
<松崎高校の1年生>
Q. このシステムはどう?
「すごいですね。自分のフォームが確認できるアプリがあまりなくて、これがあれば進化できるというか、成長できると思いました」
松崎高校には体育教諭が2人いますが、陸上を専門的に教えられる教員は不在で、日頃は外部のコーチに頼っています。アプリ導入は、教育現場で抱える「指導者不足」の解消も大きな狙いです。
<静岡県教育委員会 佐藤光浩参事>
「先生がクラス減に伴って減ってくれば、どうしても部活動を精選しなければいけないとか、そういう話になってきます。まずはそういった地域から始めていくのがよいのではないか」
県教委は、賀茂地域の高校4校について、下田高校を本校とする「サテライト制」を導入する準備をしています。
4校の連携を深めるためにはオンライン指導や学習が欠かせず、アプリ活用は地域間格差を解消する有効な一手として期待されます。