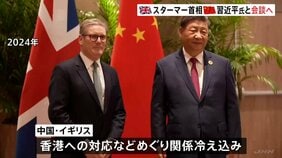国の文化審議会は、熊本県の人吉・球磨地方に伝わる「きじ馬」など、九州地方のきじ馬ときじ車の製作技術を、新たに国の無形民俗文化財に選択するよう文化庁長官に答申しました。
きじ馬ときじ車は、九州各地で親しまれている伝統的な玩具です。

このうち、人吉・球磨地方に伝わるきじ馬は、800年以上前に平家の落人(おちうど)が球磨地方に逃れ、人吉の奥地へ住み着いた際に、都の暮らしを懐かしんで作り始めたと伝えられています。
RKKに残る1961年の映像では、職人がナタやカンナで木の形を整えています。その後、車をはめ、仕上げの色付けまで一つ一つ職人の手で丁寧に仕上げられます。

この技術は今も脈々と受け継がれています。
父親から受け継いだ技術で80年以上作り続け、いまは息子も「きじ馬」作りに取り組む熊本県錦町の住岡さんは、今回の答申について。
住岡郷土玩具製作所 住岡忠嘉さん(90)「親父の遺した財産ですよね。それを私が継いでいるので、その喜びを親父に代わって私がお礼を言います」

今回の答申には福岡県みやま市や大分県玖珠町などで作られる「きじ車」も含まれ、職人の技術などとともに、古くから地域の身近な玩具として愛されてきたことが評価されました。
国の選択無形民俗文化財になると、技術を記録として残す場合などに国から助成を受けられます。
熊本県内ではこれまでに「高森のにわか」など12件が選ばれていて、今後、国の手続きを経て正式に決まります。