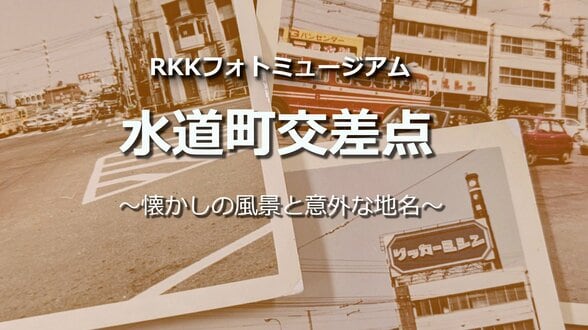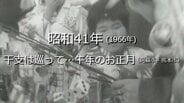平成30年(2018)3月、奥球磨の里・球磨郡多良木町(くまぐん たらぎまち)を上空から撮影しました。当時ニュースはこう伝えています。

「奥球磨とは、球磨盆地の最も東側、宮崎県との県境に位置する多良木(たらぎ)、湯前(ゆのまえ)、水上(みずかみ)の3町村を指し、‶ 球磨盆地の奥座敷 ”とも呼ばれます。

そのうちの一つ多良木町は、鎌倉時代から長くこの地方を治めた上相良氏(かみさがらし)の本拠地として栄えました。3代目の頼宗(よりむね)が1295年に建てた「青蓮寺阿弥陀堂(しょうれんじ あみだどう)」です。

石畳の参道の奥に立つ茅葺き屋根の阿弥陀堂は多良木町のシンボル的存在で、国の重要文化財にも指定されています。裏手には相良一族にゆかりある古い石碑が並んでいます。

町にあるもう一つの国の重要文化財が「太田家住宅(おおたけじゅうたく)」。特徴は鉤(かぎ)型に折れ曲がった家の形です。

江戸時代は住居の梁の長さに制限があったため鉤型に棟を増やすことで住まいの広さを確保したのです。

こちらも江戸時代に作られた碑門「百太郎堰(ひゃくたろうぜき)」と用水路「百太郎溝(みぞ)」。難工事が続き、神様のお告げによって百太郎という男性が人柱になったことからその名が付きました。

石造りの碑門は1960年にその役目を終え、移設された神社の境内から古里を見つめています。一方、百太郎溝は健在で、新たな堰から流れ出る水は今も広大な農地を潤し続けています。」