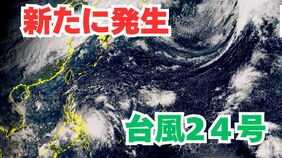入浴死のおよそ85%は自宅で起きていますが、温泉施設で発生することも。こちらの温泉では一般の人でも救命活動が行えるAEDを置いてもしものために備えています。また、寒くなるこれからの季節は館内の温度調整もこまめに行うことにしています。
(慈眼寺温泉 鶴留明子さん)「入浴するとき『きょうは寒いから気を付けて、長湯しないで』と声かけしている。(体調悪そうな人が)1時間経つけどあがってこない時、中に入って様子見ることも」
(鹿児島大学大学院・法医学分野 林敬人教授)「これは心臓の組織。こういうのを見ながら肉眼的には見えない病変がないか探す」
林教授によりますと、人口10万人あたりの入浴死による死亡率は、鹿児島はほかの県より高い傾向にあるといいます。そのため、鹿児島で始まった入浴時警戒情報ですが、今後、全国に広がってほしいと林教授は願っています。
(鹿児島大学大学院・法医学分野 林敬人教授)「警報を出すことで『お風呂に入るな』と言っているわけではない。入浴するときに普段より注意する、社会的に防ぐ必要があると思ってもらえれば、入浴死はおそらく減る」「ここからがスタート。今後、警報の効果があるかどうかを注目して見ていきたい」
入浴時警戒情報は、11月から2月末まで限定で毎日発表され、MBCテレビ、ラジオ、ホームページで公開されます。
全国のトップニュース
大谷翔平、驚愕の1試合3ホーマー!7回途中無失点で降板後に特大130m弾、“大谷劇場”に本拠地も度肝抜かれる

【独自】維新が大臣送り込まず閣外協力検討

ゼレンスキー大統領 トランプ大統領との「トマホーク」供与めぐる協議結果の説明避ける 一致点を見出せなかったことを示唆

「体調の悪化を理由に自主退職」殺人の疑いで逮捕の元職員(22) 埼玉・鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人死亡 退職から事件までの経緯を捜査 埼玉県警

関越自動車道下り 乗用車とトラック衝突で男性2人死亡の事故 乗用車の運転手(52)を酒気帯び運転と過失運転致死の疑いで逮捕 埼玉

埼玉・和光市でキックボードに乗っていた小学生の女子児童(10)が乗用車にひかれて意識不明の重体 乗用車の運転手を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕 埼玉県警

55歳男性の死体遺棄事件で大上文彦被告(50)を起訴 油圧ショベルで穴を掘り…捜査本部は事件を主導した捜査

【台風情報】「台風24号」発生 今後の進路は?雨風シミレーション&今後16日間の天気シミュレーション【気象庁 18日午前9時更新】