「浴室内突然死」という言葉をご存知でしょうか?入浴死とも呼ばれ、急激な温度変化による血圧の変化で脳梗塞や心筋梗塞などを引き起こすものです。
鹿児島県内では毎年およそ200人が亡くなっていて、この入浴死を減らそうと、気温と入浴の危険度を3段階で予報しようという研究が始まっています。
浴室内突然死=いわゆる入浴死について研究しているのは、鹿児島大学大学院・法医学分野の林敬人教授を中心とするチームです。
県内で2006年以降、入浴中やその前後に脳梗塞や心筋梗塞などで亡くなった人を示したグラフです。年間およそ200人が亡くなっていて、14年間の死者は2689人にのぼっています。その数は交通事故による死者のおよそ2.5倍です。
県警からのデータ提供を受けた林教授らが、入浴死について県内19の地域ごとに統計解析したところ、冬場に気温が低い日や、一日の寒暖差が大きい日に死亡するリスクが高くなることが分かりました。
暖かい部屋から寒い浴室に移動する際、急激な温度変化による血圧の変化で、失神したり不整脈を起こすことなどが要因と考えられるということです。
この統計データやMBCウェザーセンターが発表する予想気温をもとに、鹿児島大学大学院とMBCは共同で入浴時におけるリスクを「警戒」「注意」「油断禁物」の3段階で発表する予定で、今年の冬からテレビやラジオで伝えられるよう検討しています。
(鹿児島大学大学院・法医学分野 林敬人教授)「鹿児島県で死者を減らすという成果を得られるかどうか。アラートを鳴らすだけではなく、いい成果をもたらしてくれるのかを継続的に研究していきたいと思っているし、その結果をもって日本全国に展開していければ」
鹿児島大学大学院によりますと、10年以上かけた地域別での入浴死に関する研究は世界初とみられ、その研究結果がアメリカのオンライン学術誌に掲載されるなど、高く評価されています。
全国のトップニュース
気象庁「今後強い揺れ伴う地震のおそれ」 岩手県で震度4 津波注意報は解除
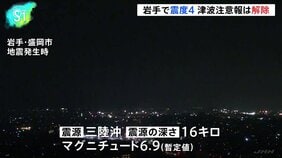
岩手沿岸部の最大10市町村、津波注意報に伴い一部地域で出された避難指示も解除
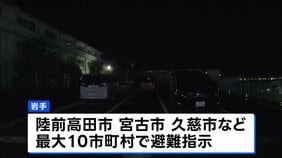
元兵庫県議めぐり虚偽情報の疑い N党・立花孝志党首 名誉毀損容疑で逮捕

ミャンマーで迫害のロヒンギャか 約100人乗せた船転覆、少なくとも7人死亡・不明者多数 マレーシア沖の海上
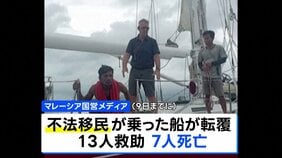
天皇皇后両陛下 三重県で「海づくり大会」行事に出席、水産高校の生徒らと交流

高病原性鳥インフルエンザ発生で約28万羽のニワトリを処分へ 新潟県内で今季2例目 新潟・胎内市

「お金を貯めたら帰国の航空券を買ってあげる」タイ人少女(12)都内マッサージ店で“違法労働”事件 娘を店に紹介した母親は台湾で拘束

1LDKが50万… NY新市長・マムダニ氏当選の背景にはトランプ氏への失望 「劇薬に期待」で左右のポピュリズムに揺れるニューヨーク【サンデーモーニング・風をよむ】
