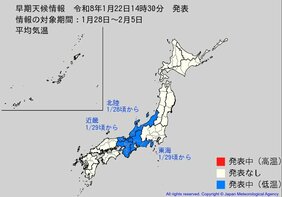きのう6月22日、霧島連山の新燃岳が7年ぶりに噴火しました。火山学の専門家は「火山は突然噴火することもある」と警鐘を鳴らします。
霧島連山の新燃岳は22日午後4時半すぎに噴火し、噴煙は火口から500メートルの高さまであがりました。噴煙は宮崎県方向に流れ、高原町では多量の降灰が確認されました。
新燃岳の噴火は2018年6月27日以来、7年ぶりです。火口から7キロ離れた霧島小学校では23日、改めて噴火に備えるよう児童に呼びかけました。
(先生の呼びかけ)「大きな噴火があったら、これまでの避難訓練を思い出して避難すること」
(児童)「(きのう)宮崎に行っていたが火山灰がけっこう降ってきて、桜島は遠いから新燃岳が噴火したと思い、びっくりした」
(児童)「いつ(噴火が)起こるか分からないから、しっかり備えたい」
学校では、教職員が改めて避難マニュアルを確認したということです。
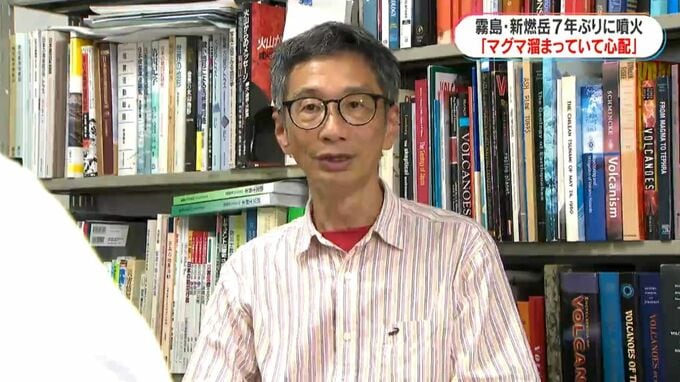
(鹿児島大学 井村隆介准教授)「新燃岳が小さな噴火で示してくれた。これが大噴火だったら人が亡くなっていたかもしれないと、みんなには受け取ってほしい」
火山学が専門の鹿児島大学の井村隆介准教授です。今回、気象台は住民からの情報提供で噴火したことを知りました。「雲で噴煙が確認できなかった」としています。
(鹿児島大学 井村隆介准教授)「爆発とともに弾道で飛ぶ噴出物は数秒以内に麓に落ちる。ということは気象庁の爆発・噴火の情報では間に合わないエリアの人たちがいる」
そして、2011年に本格的なマグマ噴火が発生したときと同じような状況になることを懸念しています。
(鹿児島大学 井村隆介准教授)「2011年の噴火の前、2018年の溶岩が出るような噴火の前には山体膨張が確認されていた。今、その状態と同じぐらい膨らんでいる。マグマはたまっているのでそれを一番心配している。普段からみんなが身の回りに気をつけておくことが一番大事」