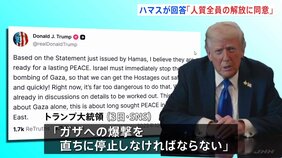「これはすごいわ!鳥肌立つ!」
入口には階段があるものの、その先は荒れた山道。道なき道を進み、急斜面をのぼっていきます。すると、隧道が出現!
(道マニア・石井あつこさん)
「これは、明治12年竣工の素掘りの隧道『牛ヶ谷(うしがたに)の地道(じみち)』。総レンガ造りの岩井寺隧道とは姿も程遠いけど、力強さを感じる」
この地域では当時、“隧道”のことを“地道”と呼んでいたことから、地名の「牛ヶ谷」と合わせてその名が付けられたそう。そして、県道38号の前身にあたるこの道は、かつて「掛川大坂(かけがわおおさか)往還」と呼ばれ、掛川市の大坂から北へ海産物や塩が運ばれていました。
隧道内の道幅は広く、「荷車を通す規格で造られた」と石井さん。重機のない時代、荷車が通れる幅を確保しながら造られた素掘りの隧道に、阿諏訪さんも「これはすごいわ!鳥肌立つ!」と大興奮。

坑口は土砂がたまっているものの貫通しており、2人は岩肌を感じながら反対側へ向かって歩いてみます。さらに、石井さんは「隧道の真上が切り通しになっている」と隧道の上を目指してのぼってみることに。
(道マニア・石井あつこさん)
「初代隧道ができる前の掘割に来るのは初めて。江戸時代から明治初期にかけて造られた道で、峠道を歩いて行ったんじゃないかな」
石井さんの「かっこいい切り通しが現存している」という言葉通り、明治12年以前に使われていた深い切り通しが今もしっかり残っています。