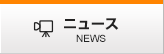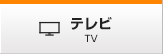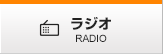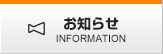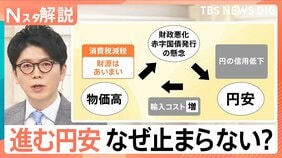ここで重要になるのが建物の耐震性です。
耐震性が高いと、共振しても建物の揺れは戻ります。
しかし、耐震性が低いと、建物が損傷して、揺れ方=「周期」がゆっくりになります。
そこへさらに同じ「ゆっくり周期」の「強い揺れ」が来た場合、共振によってさらに建物が損傷。
それが繰り返される負のスパイラルに陥った結果、最終的に倒壊に至ることが多い
と言われています。
1981年、建築基準法が改正され、それ以前は旧耐震基準、それ以降は新耐震基準と呼ばれています。
(インタ)鳥取県防災顧問 鳥取大学工学部 香川敬生 教授
「いわゆる新耐震と旧耐震では、震度6ぐらいで倒壊率が全然違ってきます」
1月の地震、奥能登地方では新耐震基準を満たした住宅が5割ほどと低く、被害拡大の要因とされています。
山陰両県の耐震化率は、公表されているデータで鳥取県は85%(2020年度)
島根県は75%(2018年度)です。