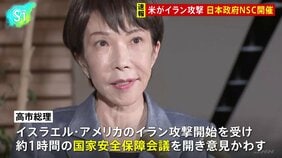大事にしていたコップをつい割ってしまった!けれど、思い入れがあって中々捨てられないということありませんか?そんな時は「金継ぎ」という方法で修復することができます。「金継ぎ」とはどのようなものなのか?その魅力を探ります。

金継ぎとは、器の割れや欠けなどを漆で接着し、その接合部を金や銀粉で装飾する修繕方法です。愛着のある器に新しい息吹を与える金継ぎは、コロナ禍によるおウチ時間の急増や、モノを大切に長く使い続けたいというニーズなどから、今静かなブームになっているようです。


青森県弘前市にある「artgalleryCASAICO(アートギャラリーカサイコ)」は、漆製品などの工芸品を中心にしたセレクトショップです。店主の葛西彩子さんは、ギャラリー奥にある工房で、漆塗り教室や金継ぎの体験講座を開催しています。


漆塗り教室の生徒からの要望で金継ぎを始めたという葛西さん。初めは、壊れた部分を綺麗に直すことだけを意識していたそうですが、東日本大震災をきっかけにその考えが変わったそうです。
※artgalleryCASAICO 店主 葛西彩子さん
「震災をきっかけに、ただモノを直すというだけじゃなくて、皆さんの思い出の修復みたいな、そんな気持ちで私の力が役に立てばなっていうふうに変わっていきました」
持ち込まれた器には、持ち主のストーリーがあり、値段は付けられない「モノの価値」があると身にしみて感じたといいます。
■漆のチカラを活用する「金継ぎ」
金継ぎに欠かせないのが漆です。
ウルシノキから採取される漆は、日本では縄文時代に既に使われていました。塗りあげた時の美しさから工芸品の塗料としても発展。青森県を代表する工芸品、津軽塗にも使われています。
もともとは塗料であるこの漆を、金継ぎでは接着剤として活用するのです。


■「金継ぎ」の工程
まずは接着剤を作ります。使用するのは本漆。これに、小麦粉や、砥の粉(石の粉)、木の粉などの天然素材を加えて練り上げます。



欠けた部分を接着させたら、漆を乾かします。漆の性質を利用し、温度20~25度、湿度70~80%の室で、ゆっくりと硬化さます。固まったらヤスリで整え、継ぎ目に重ねて漆を塗り、最後に金の粉を撒き装飾して仕上げます。




■「金継ぎ」で生まれる新たな“景色”
金継ぎをした箇所は傷ではなく「景色」と呼びます。器の割れ目に金を施し、新しいデザインで、生まれ変わるのです。

※artgalleryCASAICO 店主 葛西彩子さん
「1回壊れてしまったものは、どうやって綺麗に直しても元には戻らない。なので(金継ぎには)傷ついてしまったその傷も含めて愛しむというか、傷を受け入れながらプラスにしていきましょうという、日本人ならではの精神美みたいなものが入っています」
日本で古くから使われている天然素材の漆を使い、壊れた器が生まれ変わりました。

愛着ある器に新な価値を生み出す「金継ぎ」は、モノを大切に長く使い続けようとする現代のSDGsの考え方にも通じるのではないでしょうか。
artgalleryCASAICOでは、一日体験もできます。興味のある方は一度体験してみてはいかがでしょうか?

artgalleryCASAICO
住所 弘前市城東中央4-2-11
TEL&FAX 0172-88-7574
1DAYかんたん金継ぎ体験 4500円
完全予約制 ※5日前までの予約
当日持ち帰り
日時 月~土 2時間
人数 2名様以上(5名様以上で出張講座も可能)