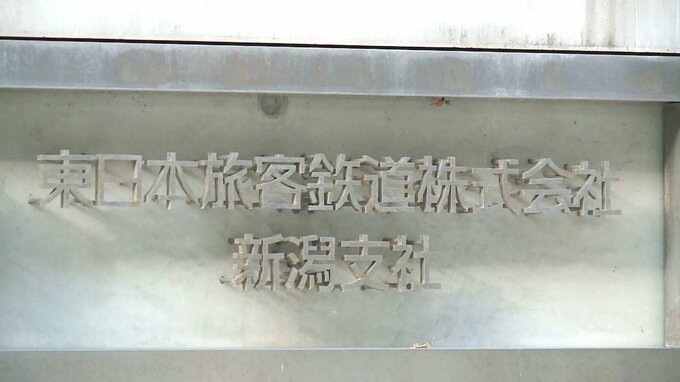JR東日本は、2022年度に利用が少なかった路線について、1日の平均乗客数にあたる「輸送密度」が2000人以下となった地方路線の収支などを公表しました。
2000人以下だったのはJR東日本管内の35路線66区間で、その全てが赤字となりました。新潟県内では8路線11区間で赤字となっていて、羽越線の村上-鶴岡(山形県)間は、収支が初めて公表された2019年度以降、4年連続で年間約50億円の赤字となるなど厳しい収支が続いていてます。
赤字額が最も大きかったのは、羽越線の村上‐鶴岡間で49億円4600万円でした。
赤字額が大きい理由として、県境をまたぐ区間で学生の利用者が少ないことや
長距離を走る列車や貨物列車があり、雪や潮風などに対するメンテナンス費用がかかることなどを挙げています。
県内の路線で次に赤字額が大きかったのは、上越線の越後湯沢-水上(群馬県)間で19億2000万円、次いで磐越西線の津川-五泉間で11億2600万円でした。
一方で、経費に対する運賃収入を示す「収支率」で見ると、新潟県内で最も低かったのは磐越西線の津川‐野沢(福島県)間で0.7%、飯山線の津南-戸狩野沢温泉(長野県)間で、0.8%、只見線の小出-只見(福島県)間で2.6%と続きます。
収支の厳しいローカル線については10月の法改正で、バスなどへの転換も含めた「地域公共交通の再構築」をするため、交通事業者と沿線自治体が話し合った上で3年以内に結論を出すべきとする「再構築協議会」の設置が可能となりました。
JR西日本は10月に全国で初めてこの制度を利用し、利用が低迷しているJR芸備線の一部区間で「再構築協議会」の設置を国に申請しています。