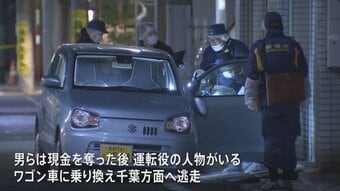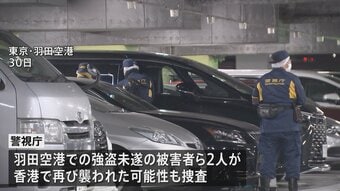北海道の知床半島沖で沈没した観光船「KAZU I」の事故について、国の運輸安全委員会が事故原因などをまとめた最終報告書を公表しました。
去年4月、知床沖で観光船「KAZU I」が沈没した事故では20人が死亡、6人が行方不明となっています。
この事故について調査を進めてきた国の運輸安全委員会はきょう、およそ200ページにわたる事故の最終報告書を公表しました。
この中で、事故の直接的な要因として、船首部分にあるハッチを密閉するための留め具が十分に締まっていないまま航行し、それにより海水が流入したことで浸水が拡大した可能性を指摘しました。
ハッチについては同業他社の社員が事故の2日前に行われた訓練に参加した際、ハッチのふたが、およそ3センチ浮いている状態だったと証言しています。
また、事故当日には同業者から「海が荒れる」と警告を受けたにもかかわらず、経験の浅かった船長が出航の判断をしていて、船長が知床海域で船を操縦するのに必要な知識や経験がなかったと考えられると指摘しました。
そのうえで、「ハッチに不具合がある状態でも船長が海象が悪化した海域を航行することがなければ、事故には至らなかったと考えられる」としています。
一方で、事故の間接的な要因としては▼国の代行機関で小型船舶を検査する日本小型船舶検査機構=JCIが、事故の3日前にハッチを検査した際に開閉検査を省略したこと。▼北海道運輸局が会社に監査を行った際に安全管理体制が十分でないことを把握して、改善を求められなかったことをあげました。
そして最後に再発防止策として、事業者に対して航行する海域の特徴を十分理解している人を運航管理者に選ぶなど、安全管理体制を充実させることを求めたほか、国交省に対しては監査の実効性を高めることなどを求めました。
注目の記事
「コメを自宅で炊く」のも節約ポイント! 大学生の生活費は月13万円超 家賃より「防犯・設備」重視?変化する若者の1人暮らし事情

“爪切りの頻度” が減ったら体からのSOS…? 飲酒や喫煙など生活習慣も原因に 指先の数ミリの成長が示す「体調の履歴書」メカニズムは?

SNSで「超激レア」と話題!高岡で見つかった“おばあちゃん標識”の正体は45年前の「愛」だった…

高い致死率「ニパウイルス」アジア各国で流行の懸念 ワクチン・特効薬なし…日本への流入リスクは?【Nスタ解説】

政策アンケート全文掲載【衆議院選挙2026】

「今日の雨おかしい」中学生を動かしたのは気象予報士の“10年前の後悔” 100回以上続く命の授業