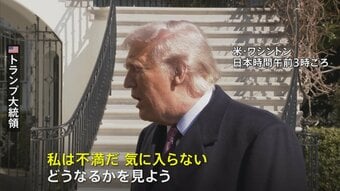障害者割引の“あり方”は? 当事者たちの声から考える

久保田編集長:
福祉のあり方も変わっていると思うんですけれども。では、当事者の皆さんはどう感じているんでしょうか?
障害者団体A
「ひとりで鉄道に乗れる=自立している。普通運賃を支払うのは正しいと思う」
障害者団体B
「障害者には多くの金銭的負担がある。(単独利用での割引は)不平等ではない」
小川キャスター:
一口に障害者といっても、障害のあり方は様々ですからね。受け止め方も様々かもしれないですね。
久保田編集長:
どちらの意見も本当だと思うんですよね。中には切実な方もいらっしゃるということもわかると思います。
それでは今後、割引の適用の拡大という考えはないんでしょうか?JR東日本にききました。

JR東日本 担当者
「割引の拡大は、他の客の負担増にもつながるため、現在考えていない」
「国の社会福祉政策で行われるべきものと考えている」
つまり割引するには「負担をどうするのか?」という話に繋がってくるわけです。
山本キャスター:
「誰が払うのか」となってくるわけですね。電車に普段乗っていても、車椅子の方がお1人で乗ってらっしゃる姿も、よくお見かけしますし、障害のある方の生活のあり方も変わってきていると思うんですよね。ただ障害の程度によっても違ってくる、見えてくる景色が違ってくるから、一言ですぐに解決できない話だなと思いますね。
小川キャスター:
難しいとは思うんですけれども、でも鉄道各社がわからないまま、前例を踏襲し続けるというのは、やっぱり変わっていかなきゃいけないのかなと思いますし、割引のあり方というのは単純に経済的な負担の軽減だけではなく、社会がどう障害のある方に向き合おうとしているのか、そのメッセージでもあると思うんですよね。
久保田編集長:
最近、合理的配慮という言葉もよく使われるようになりましたよね。バリアフリーも進んだと思うんですけど、「料金についてはどう考えるのか」、今回のケースをきっかけにして、考えてみたいなと思いますね。皆さんは、どうお感じになるでしょうか。