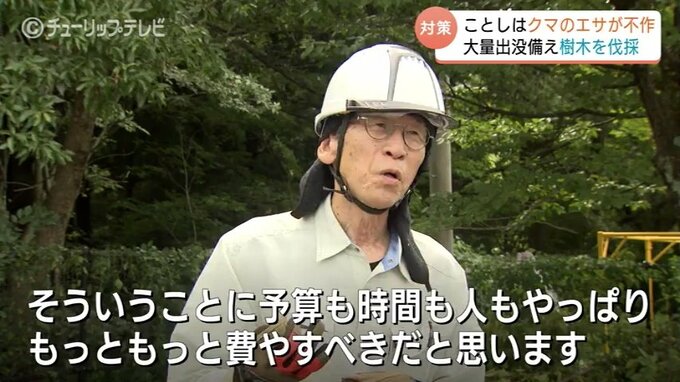餌不足から人里でクマの大量出没が懸念される中、富山市の細入地区では保育所周辺でクマのエサとなる木の伐採作業が行われました。人身被害を防ぐ水際対策が進む一方、専門家は「駆除の方法の議論ではなく予防策に人や予算を費やすべき」だと中長期的な視点で警鐘を鳴らしています。

保育所のすぐそばに生えた樹木。

高さおよそ15メートルのこの木はミズキという品種で、ツキノワグマやニホンザルがエサとして好む実がなります。

12日は細入地区の自治会のメンバーら5人が、この時期から増えるクマ出没の対策としてミズキやオニグルミを伐採しました。

自治会がこうしたクマ対策での樹木の伐採をおこなうのは初めてだということです。

ことしは、県全域でクマが好んで食べるブナが凶作、ミズナラやコナラが不作でいずれも去年より実りが悪い状況となっています。

県は9月4日、クマがエサを求めて標高の低いところまで活発に活動することが懸念されるとして、今シーズン2度目となるツキノワグマ出没警報を発表。

クマのエサとなる樹木を伐採し、クマの誘引物を除去するなど対策を呼びかけています。
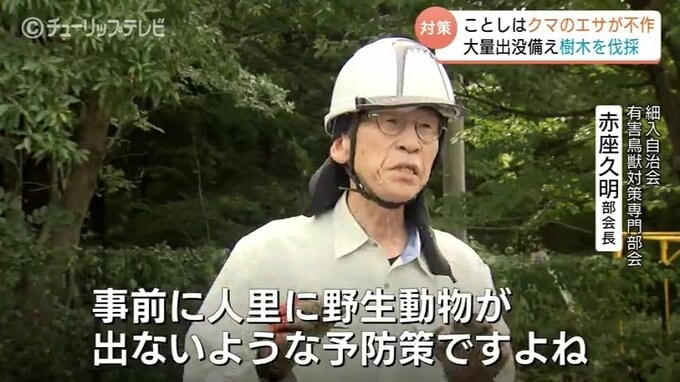
細入自治会 有害鳥獣対策専門部会 赤座久明部会長
「事前に人里に野生動物が出ないように予防策ですよね。そういう被害があったらとりあえず外出は控える。身の回りの誘因物を片付ける。戸締りをしっかりする。個人でできることを精いっぱいやっていただきたいんですね」
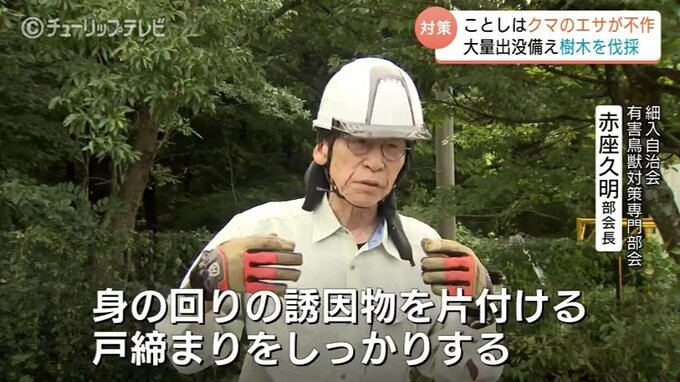
県自然博物園ねいの里に務め、クマの生態に詳しい赤座さん。行政には、こんな注文も。
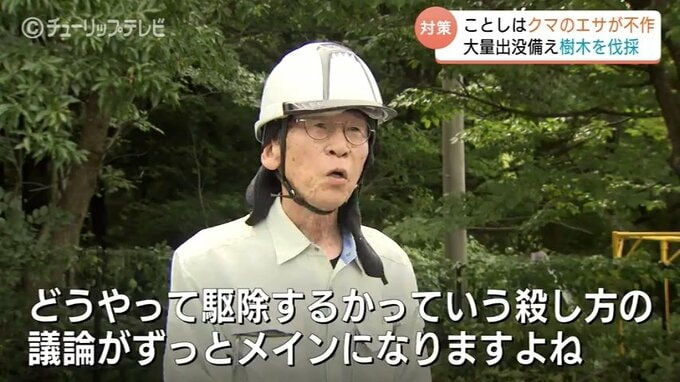
細入自治会 有害鳥獣対策専門部会 赤座久明部会長
「どうやって駆除するかっていう殺し方の議論がずっとメインになりますよね。それは緊急事態の時にはそうしなきゃいけない。それはわかるんですけど実際集落の中にクマが入ってしまったらそれでもうやれることは限られてるんですよ。人里へ野生動物が出ないようないわゆる予防策ですよね。そういうことに予算も時間も人もやっぱりもっともっと費やすべきだと思います」