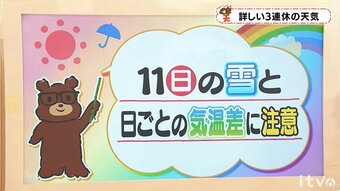(高齢男性の参加者)
「もう相続が年齢的にも近いから、円満にちゃんとしておこうと思って」
(40代女性の参加者)
「まだまだ先かもしれないがやっぱり今後の自分の人生の中で必要となってくる。若いうちからやらないじゃなくて、勉強しておく。そういうのもひとつかなって。それが『終活』なのかなと思って」
人生の最後を見つめ、亡くなった後に備え準備をする“終活”。遺言書の作成もその一つです。
遺言書には、主に自分で書く自筆証書遺言と、公正証書遺言の2種類があります。
公正証書遺言は、公証役場で法律の専門家である公証人に作成してもらう遺言です。専門家が作成し、公証役場で保管してくれるので信頼性が高い遺言ですが、作成には財産の価格に応じた手数料が必要となります。
(※手数料…財産の価格によって変わるが、一般的なケースで多いのは4~5万円程度)
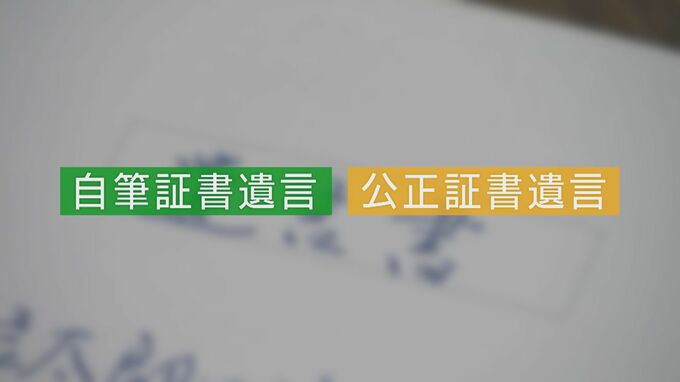
一方、自筆証書遺言はすべて自分で作成するので費用はかからず、手軽で自由度の高いのが特長です。
しかし…
「遺言書があることを知らなかった」
「遺言書がなくなってしまった」
「遺言書の内容を誰かが書き換えた」
自筆の遺言書は自宅で保管されることが多く、相続する人に発見されず紛失してしまったり、親族などによって改ざんされたりする恐れもあります。
(松山地方法務局 供託課 守屋文貴課長)
「せっかく遺言書を書かれたとしても、その思いと違う遺言書となってしまうということは、やはりその方にとってマイナスだし、人生最後の引継ぎのバトンをしっかりと確実に送っていただきたい」
こうした中あらためて注目されているのが、法務局が自分で書いた遺言書を保管してくれる自筆証書遺言書保管制度です。
2020年から始まったこの制度を利用すると、法務局が遺言者本人が亡くなってから50年間、遺言書の原本を厳重に保管してくれるので紛失や改ざんの心配はありません。
また本人が亡くなると、相続人に対して遺言書が保管されていることを通知してくれます。
愛媛県内では、毎月15人程の保管の申請があるというこの制度。この日も女性が、遺言書を保管するための手続きで法務局を訪れました。

「遺言書を法務局に預かってもらう制度ということで、ご存じでしたか?」
(申請に来た高齢女性)
「新聞で前見たんです。それで知っていた。まあ遺言書をしておいた方が何かあった時にいけないから」
(松山地方法務局 供託課 守屋文貴課長)
「遺言書がないとやはり法定相続となりますので、そうなると本来その財産をあげたくなかった人にもあげざるを得ないという事も生じますので」
残された家族などへ自分の意思を託す遺言書。先の事を見据え、思いをカタチにしておく必要がありそうです。