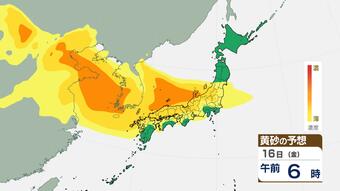様々な理由で親と暮らせない子どもは全国でおよそ4万人を超えるとされています。国は特定の大人と愛着関係を築く「里親制度」を推進していますが、その委託率で日本は外国に大きく後れを取っています。なぜ里親制度は広がらないのか?不妊治療をきっかけに里子を迎えた家族から、現状の一端を学びます。
「これば1回混ぜて」「これ?」「これ全部?」
台所で一緒に料理をする親子。
長崎県に住む小学5年生の女の子と母の千賀子さんです。

Qお手伝いはよくする?
母・千賀子さん:
「はい。家にいるときはね。サッカーで忙しくて」
女の子:
「もともとお兄ちゃんがサッカーをしていたので」
Q、V・ファーレンの試合も見に行く?
「家族で見にいったり、(兄と)2人で見にいったり」
阿部さんはおよそ8年前、当時2歳だった女の子の里親になりました。
「里親制度」とは、親の病気や離婚などで家庭で生活できない子どもを迎え入れて養育する制度です。原則子どもが18歳になるまでで、法的な親子関係はありません。そして里親となるのに、特別な資格は必要ありません。

「いただきます」
阿部家には現在、実子の高一長男(15)、里子として迎えた女の子(10)、里子として迎えた男の子(3)の3人の子どもがいます。
阿部さんが里親について考え始めたのは30歳の頃。2人目の子どもがなかなか授からない…、その悩みの中にいた時でした。

阿部千賀子さん(49):
「元々子供が大好きっていうのもあったんですけど不妊治療を長くして、でもちょっと諦めないといけないなっていうときに、たまたま里親制度のことを知って」