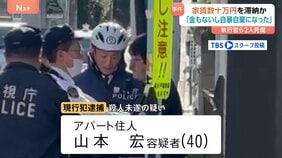連日厳しい暑さが続く中、熱中症の疑いでの救急搬送が増加しています。救急医療が専門の医師は、室内の過ごし方に特に注意が必要と呼びかけています。
山口大学医学部付属病院先進救急医療センター 鶴田良介部長
「コロナから避けようとして孤立すると、今度は熱中症になっていくというような事にもなります。非常にこの辺がコロナの3年間で生活様式も変わったりして、そして今年は本当に極端に暑いんで、熱中症が起こりやすい条件がそろっていると思います」
山口大学医学部付属病院救命救急センターの鶴田良介医師は、近年見られなかった熱中症の重症患者が、今年は見られるようになったと話します。熱中症には「労作性」と「非労作性」の2種類あり、「労作性」は、肉体労働やスポーツなど屋外で体を動かしている時に、「非労作性」は室内での日常生活の中で起こります。
鶴田医師
「搬送件数が増えているのは、非労作性。ふだんの生活をしながら屋内で熱中症になっている方々たちでこれも圧倒的に高齢者」
7月に山口県内で熱中症の疑いで救急搬送されたのは308人で、去年の同じ時期に比べ66人多くなりました。そのうち65歳以上の高齢者は192人と6割以上を占めています。熱中症が発生した場所は、住宅が最も多い125人でした。
鶴田医師
「高齢の方で暑いと感じない。そういった暑さに対する感受性が鈍っている方がいらっしゃるんですよね。だからエアコンをつけない。外出しなければいいという訳ではなくて、ふだんの生活の中でも、例えば温度計をよく見るとか」
対策として、経口補水液やスポーツ飲料など、塩分やミネラルが入った水分をこまめにとることや、エアコンを使って適切な温度と湿度を保つことなどが挙げられます。特に高齢者は、気づきにくい場合もあり、家族や近所の人などが気を配る必要があります。また、外出する場合は白い服や通気性のよい服を着て「クーリングシェルター」を利用をし、休憩を取るよう呼びかけています。
鶴田医師
「図書館とか、場合によってはコンビニエンスストアとか、そういった所に行って涼んでもらって、夕方になると帰る。そうするとそういう所に集まって安否確認もできる」
食欲がない、活気がないなどの症状は、熱中症の初期症状の可能性があり、かかりつけ医に相談してほしいとしています。