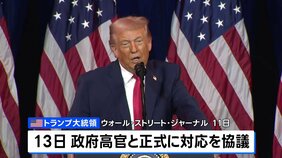市が発注した工事で官製談合をしたとされる男2人の裁判。市職員の男(72)と、塗装会社役員の男(79)の間でどんなやりとりがあったのか。裁判を傍聴した取材メモからひもときます。
官製談合防止法違反などの罪に問われているのは元・山口県岩国市職員の男と、塗装会社役員の男です。起訴状によりますと、2人は2020年に行った市の供用会館の改修工事を請け負う業者を決めるための「見積り合わせ」2件で、共謀して見積金額を決めた上で、会社役員の男の提案した2社を相手業者に選び、男の会社に契約させたとされます。また、市職員の男は2019年に行った3件の「見積り合わせ」でも、同様の手口で入札の公正を害したとされます。
16日、山口地裁で開かれた初公判で、起訴内容を認めた2人。検察の冒頭陳述で、2人が犯行に手を染めたいきさつが明らかになりました。
2005年~2006年ごろ、当時外壁工事の担当をしていた市職員の男は、会社役員の男の会社が工事を受注したことをきっかけ知り合いました。その後2010年頃から、会社役員の会社を見積もりあわせの会社として指名するようになりました。
その中で会社役員の男は、市役所や工事現場で市職員の男と顔を合わせたり、電話で話したりする機会も多くなります。遅くとも2013年ごろからは、市職員の男に対して毎年のように、中元歳暮の時期にハムの詰め合わせなどを贈っていました。市職員の男が定年した直後には、江戸切子ペアグラスやカタログギフトを「退職祝い」として贈っていて、それを利用して市職員の男は妻と、旅行に行ったということです。
ではなぜ、会社役員の男が談合しようと思ったのか。
会社役員の男の会社には“積算ソフト”がなく、入札では積算能力の高いほかの企業に契約を取られる状況だったことなどから、入札ではなく「見積り合わせ」で決まる工事をより多く受注したいと思うようになり、2011~12年ごろ市職員の男に、他の相見積もり業者を提案することや、これらの業者の見積もりもとりまとめて提出することを提案しました。市職員の男は不正が発覚しないよう、見積金額を予定金額の90%程度になるよう、話し合って決めていました。こうして、確実に会社役員の男の会社が受注できる「出来レース」状態となり、2010年以降、市職員の男が発注する随意契約による工事のほぼ全件を、会社役員の男の会社が受注するようになったといいます。
裁判で「間違いありません」と起訴内容を認めた2人の容疑者。今後の裁判で、検察官から求刑される予定です。