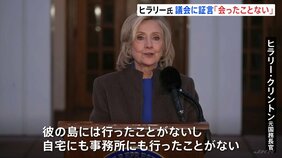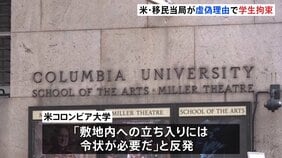5月8日から、新型コロナの感染症法上の分類が「2類」から「5類」に引き下げられます。小中学校や高校などが感染した児童や生徒に求めている出席停止の期間は「発症日から5日間、かつ症状が軽くなってから1日経過するまで」とする方針です。学校現場はどう受け止めているのか、取材しました。
福島市の桜の聖母学院小学校。市内各地から児童が登校しているため、新学期に入ってからも児童全員がマスクを着用しています。
この小学校では、5月8日の5類引き下げ以降も、黙食などの対策を続けたまま、マスクの着用については個人の判断に任せる方針です。一方、出席停止の期間が7日から5日に短縮されることについては、教育機会の確保という点で、前向きにとらえています。
桜の聖母学院小学校・武藤浩之校長「(これまで)7日を待たずに体調が回復した児童がほとんどだった。7日から5日に短縮されるという方針は学校側としては前向きに受け止めている」
また、5類引き下げ以降は感染者と接触しても、濃厚接触者として外出の自粛が求められないため、家庭で感染者が出ても児童は基本的に登校できるようになります。しかし、家庭によっては判断が異なる可能性もあり、学校では家庭の状況などに合わせて対応する予定です。
武藤浩之校長「(例えば)子どもの健康を懸念して休ませたいとなったら、学校側としては欠席ではなく出席停止にする方向で考えている」
5類への引き下げ以降、子どもの学校生活についても判断が個人に委ねられる場面が多くなるため、学校では、これまで以上に柔軟な対応が求められることになります。
武藤浩之校長「基本的な方針は大事だが、それに全てとらわれずにケースバイケースで柔軟に対応していくことが必要」