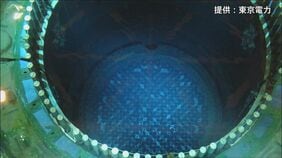台湾東部・花蓮県の近海を震源地としたマグニチュード7.7の大地震は発生から1週間が過ぎた。台湾政府の発表によると、4月11日時点で死者は16人、けが人は1,100人。行方不明者が3人いる。東アジア情勢に詳しい、飯田和郎・元RKB解説委員長は11日に出演したRKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』で、「地震をめぐる世論戦」という側面でコメントした。
国際社会の世論を「味方に付ける」戦い
台湾東部・花蓮県の近海を震源地とした大地震は4月10日で発生から1週間が過ぎた。ただ、復興は長い時間を要することになりそうだ。台湾や中国を長年、ウォッチしてきた者の悪い癖かもしれないが、少し違った角度から、この地震災害を分析してみたい。
それは「世論戦」とでも言おうか。つまり、台湾の立場からすると、地震という悲惨な出来事に、どう立ち向かうか。それを、国際社会に「知ってもらう」、国際世論を台湾に向ける戦い。国際社会の世論を「味方に付ける」戦いと言ってもよい。
台湾の被災者への同情を寄せる「二つの近さ」
今回の地震に関する報道を、日本から見ていると、私は改めて日本と台湾の「近さ」。それも「二つの近さ」を感じる。
一つは距離的な近さだ。もともと日本の新聞社や通信社、放送局は台湾に特派員を置いている。それに加え、日本からも地震発生直後から取材陣が震源地の花蓮県に入っている。日本を含めた海外から台湾へ取材に入る場合、本来は取材ビザが必要だが、今回は多くがノービザだろう。厳密には、ルールを逸脱しているが、台湾当局も、それはわかっていて見逃しているのだろう。むしろ、取材してほしい、という思いもあるはずだ。
もう一つは、社会のシステムや価値観の「近さ」だ。日本と台湾は社会システムが似ている。日本のメディアも、ほかの外国での取材に比べ、難易度が高くない。なにより、余震が頻発するという危険な状況のなか、やってきた海外の取材クルーに、当局はさまざまな便宜を図ってくれている。日本への親近感が強い台湾の住民たちが取材に協力してくれているようだ。
そうなると、日本を含む海外メディアが被災地から発信する量が増える。ニュースの内容も濃くなる。そして、それを日本のラジオのリスナーや、テレビの視聴者、新聞を手にした人が見たり、聴いたりする。さらに震災への関心が高まり、台湾の被災者への同情を寄せる。
実際、地震発生直後から、日本国内では「今こそ、台湾に恩返しをする時だ」という声が上がった。元日に起きた能登半島地震では、台湾からたくさんの義援金が寄せられ、わざわざ台湾から炊き出しに来てくれる人もいたからだ。
築かれた交流の延長で連携、連鎖を生む
誤解のないように聞いてほしいのだが、今回の地震での犠牲者や被害は、海外で起きた災害としては、過去に日本のメディアが伝えたものに比べても特段、甚大ではない。だが、日本では連日、報道されてきた。さきほど説明したように「距離的な近さ」、それに「社会システムやお互いの感情の近さ」。メディアの特性だろう。そうなると、報道はやはり好意的なトーンになる。
現地に入った海外メディアは、被災者が滞在する体育館に、個室式テントが用意されたり、食料が十分に提供されたりしていることなどを伝え、当局の迅速な対応を評価する報道も多い。
さかのぼれば、2011年の東日本大震災では台湾から200億円以上の義援金が寄せられた。そのほとんどが個人を含めた民間からの義援金だった。新型コロナウイルスが日本で蔓延し始めた当初、台湾からは日本で不足していたマスクが贈られ、のちには台湾で足りなくなったワクチンが日本から台湾へ寄贈された。
多くの死傷者や、多大な被害が出た今回の地震は不幸なことだ。ただ、メディアの報道の話から始めたが、この地震によって、日本と台湾の間で、良好な連携、連鎖を生むことにつながっている。それも、これまで築かれた交流の延長にある。