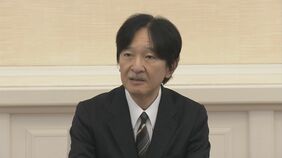13年前の東日本大震災や、今年1月の能登半島地震では、倒れた家具による被害が多くみられました。東京消防庁によりますと、2003年以降の大規模災害でケガをした人のうち、30パーセントから50パーセントが家具の転倒・落下が原因でした。命に直結する家具の固定化。大分県内の現状と対策のポイントをリポートします。
家屋の倒壊など、甚大な被害が広がった能登半島地震では、屋内で家具の転倒によるケガ人も相次ぎました。
(県防災対策企画課・村山奉勝さん)「家具が転倒すること、もしくは移動することで通路を塞いでしまう。火事が発生した時に逃げ道を失って、亡くなってしまう危険がある」
有効な防災対策としてあらためて指摘されたのが「家具の固定化」です。2022年度の県内の固定化率は50パーセントで、目標値をクリアしていますが、課題もあります。
(県防災対策企画課・村山奉勝さん)「ここは固定出来ているけれど、ここは出来ていないとかそういった家具の固定に関しては様々な実態があるのではないかと思っています」
家具を固定する際のポイントを防災士として活動する専門家に聞きました。
(県防災活動支援センター・山村利貞副理事長)「今の家は石膏ボードが多いので機械で下地(柱)を探します」
壁の裏には、通常、柱と壁を支える間柱といわれる柱があります。この柱がどこにあるか、市販の専用の工具で確認します。その位置に合わせてL字金具で取り付ける事で転倒を防げます。
(山村利貞副理事長)「上と横を固定した方がいい壁と、一体型に家具があるので地震の時に動かない」
一方、大分市のホームセンターでは賃貸などのため、壁に穴をあけらない家を対象にした商品も取り揃えています。伸縮棒や転倒防止マットのほか、食器の落下を防ぐものもあります。こうしたグッズを組み合わせて使用することがより効果的です。
(ハンズマンわさだ店。本村綾司副店長)「災害があった時に、家具が転倒したりとか、物が落ちたりとかでケガされることもあるので、あの時しておけば良かったなと後悔されるよりは、今のうちから対策をした方がいいと思います」
身近で有効な防災対策といえる家具の固定化。自分と家族の命を守る備えの第一歩です。