サツマイモが収穫期を迎えていますが、ここ数年、深刻な被害をもたらしているのが基腐病です。その特効薬になるかもしれません。鹿児島大学などが、基腐病に有効な微生物の研究・実験を重ねています。その現場を取材しました。
(鹿児島大学 前田広人・名誉教授)
「去年よりいいけど、まだ完璧ではないですね」
微生物が専門の鹿児島大学・前田広人名誉教授です。肥料などを開発する企業と共同で、3年前から基腐病の研究を続けています。
(前田名誉教授)
「健全な土壌を作って、その健全な土壌を元に、イモがよくできるかどうかを試している」
基腐病は、菌に感染したサツマイモの茎や根が腐る病気で、県内では2018年に初めて確認されました。被害は年々拡大していて、基腐病が疑われる症状が一株でも確認された畑は、去年は、作付面積全体のおよそ75%に上っています。
(※2021年74.5% ※2020年54.1% ※2019年46.2%)
水はけの悪い場所に繁殖しやすいことが分かっていて、県は、排水や苗の消毒など対策を呼びかけていますが、時間も費用もかかるため、被害を抑え込めていないのが現状です。
効果的な解決策はないか…。鹿児島大学などのチームが注目したのが「微生物」です。
(前田名誉教授)
「基腐菌を攻撃する微生物を植えつけた」
シャーレの中央にあるのが基腐病の菌です。実験ではその周りに数種類の微生物を植えつけます。通常、繁殖力の強い基腐れの菌は白く広がりますが、菌に強い微生物の場合、増殖が抑えられているのがわかります。
研究チームはこれまでに、微生物の中から200種類ほどを試し、基腐病の菌の繁殖を弱める微生物を特定しました。
(前田名誉教授)
「効く菌を培養して、色んな形で畑の中にまいて、実際に基腐れを抑えるかを現場でする」
研究チームは、酒造会社や農家から実際に基腐病が発生したサツマイモ畑を借りて、実証実験を行っています。特定した微生物を土に加え、時期や量を変えながら取り組んだ結果、基腐病にかかったイモの割合は、最も成果があった畑では1年目が90%だったのに対し、2年目が15%、3年目のことしは2%まで抑えることができました。
研究チームは現在、この微生物を含んだ液体タイプの土壌活性剤を開発中で、病気の発生した畑に撒き、その効果を検証しています。
研究に協力している農家の中野昇さんです。4年前に基腐病が発生し、収穫量は6割減りましたが、研究の成果に期待しています。
(農家 中野昇さん)「1年1年効果が出ている、楽しみが出てきた。期待している」
土の中の微生物を遺伝子レベルで解析する研究も行っています。基腐病が発生した畑の土に含まれる微生物の数や、遺伝子配列を解析し、種類を特定。1グラムの土の中には、およそ1億の微生物がいるといわれていますが、畑がどんな状態であれば基腐病が発生しやすいのかを調べています。
(鹿児島大学 奥西将之・准教授)
「微生物が有効であるとわかったら、微生物がどれくらいの頻度で、どれくらいの量を入れれば、ずっと微生物が畑の中にいられるかも分かる。今は菌を入れたきりで、どうなっているかわからないので、そういうところは、これ(遺伝子の解析)でしっかり抑えられると思う」
研究チームが開発中の土壌活性剤は、早ければ再来年、2024年の春に商品化する予定です。
(前田名誉教授)
「ベストスコアでいうと7割ぐらいまで」
Q.1年半後の完成に期待してもいい?
「約束はできないが、努力はする」
生産量日本一の鹿児島のサツマイモを基腐病から救えるのか?目には見えない小さな生き物に大きな期待がかかります。
全国のトップニュース
高市総理 きょう与党幹部に“解散の意向”伝達か 「2月8日投開票」日程を軸に調整進む
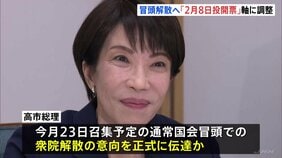
【速報】神戸6歳児虐待死事件 「外に出られたら遺骨を迎えに行きたい」と述べた母親に対して懲役4年 叔母2人に対して懲役3年、執行猶予5年の判決 神戸地裁

【速報】日経平均 一時900円以上値上がり 初の5万4000円台を突破 選挙意識の“高市トレード”続く

【速報】2026年「歌会始」 初出席・悠仁さまはトンボの歌詠む 皇室12人の全歌一覧 お題は「明」 天皇陛下は元日の星空を歌に寄せ

【最新】「あすは彼氏と過ごす」遺体で見つかった女性看護師が行方不明前日に祖母と会話【壁の中から女性遺体】逮捕された飲食店経営者とは親しい間柄

【気象情報】14日にかけて北日本・北陸は大荒れの天気に 急速に発達する低気圧の影響で暴風雪や大しけ予想 15日も北海道は継続して警戒【雪と雨のシミュレーション】

イラン反政府デモ 死者2500人超に トランプ大統領はデモ継続を呼びかけ「国家機関を乗っ取りなさい」

誤って約5,900万円二重徴収 徴収済み3897件の水道料金引き落とし 20日にも返金対応 今後は複数人チェックで再発防止へ 富山・小矢部市

