5年に1度の「和牛のオリンピック」=全国和牛能力共進会が6日開幕します。前回、日本一に輝き52年ぶりに地元開催となる鹿児島が好成績を残すのか?関係者の期待は高まっています。
鹿児島で52年ぶりに開かれる大会には、過去最多の41の道府県からおよそ440頭が出場します。大会は「種牛の部」と「肉牛の部」の大きく2つに分かれ、1頭のみや3世代1組など9つの区分で競われます。特に、種牛と肉牛の7頭1組で審査される6区は「花形」で、ニーズの多様化に伴い新設された脂肪の質に注目する7区は、今大会の「目玉」です。
霧島市牧園町で開かれる「種牛の部」で審査のポイントとなるのが、発育の良さや体形です。胴の長さや幅など肉になる部分の体積が大きいほど高評価ですが、大きすぎると飼料代がかさむために月齢に応じた発育が求められ、姿や形の美しさも重視されます。
南九州市知覧町で開かれる「肉牛の部」では肉の量や質を評価。口溶けの良さや、うま味などにつながる成分の量を測ります。
鹿児島は前回、総合順位で全国1位でしたが、今回は総合順位をつけないため、各審査区分でのトップや、種牛と肉牛の部で、最も優れた牛に贈られる内閣総理大臣賞の獲得を目指します。
(全国和牛能力共進会県推進協議会 坂元信一推進委員長)「前回以上の成績をとれるように、農家や関係者で」
期間中、全国のブランド牛の試食など一般客向けのイベントも開かれ、前回の宮城大会ではおよそ40万人が来場し、およそ100億円の経済効果があったとされます。九州経済研究所は新型コロナの影響で来場者は減るものの、今回はおよそ43億6000万円の効果を試算しています。
関係者の期待も集まる大会は6日から今月10日まで、5日間開かれます。
全国のトップニュース
高市総理 きょう与党幹部に“解散の意向”伝達か 「2月8日投開票」日程を軸に調整進む
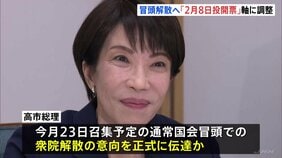
【速報】神戸6歳児虐待死事件 「外に出られたら遺骨を迎えに行きたい」と述べた母親に対して懲役4年 叔母2人に対して懲役3年、執行猶予5年の判決 神戸地裁

【速報】日経平均 一時900円以上値上がり 初の5万4000円台を突破 選挙意識の“高市トレード”続く

【速報】2026年「歌会始」 初出席・悠仁さまはトンボの歌詠む 皇室12人の全歌一覧 お題は「明」 天皇陛下は元日の星空を歌に寄せ

【最新】「あすは彼氏と過ごす」遺体で見つかった女性看護師が行方不明前日に祖母と会話【壁の中から女性遺体】逮捕された飲食店経営者とは親しい間柄

【気象情報】14日にかけて北日本・北陸は大荒れの天気に 急速に発達する低気圧の影響で暴風雪や大しけ予想 15日も北海道は継続して警戒【雪と雨のシミュレーション】

イラン反政府デモ 死者2500人超に トランプ大統領はデモ継続を呼びかけ「国家機関を乗っ取りなさい」

誤って約5,900万円二重徴収 徴収済み3897件の水道料金引き落とし 20日にも返金対応 今後は複数人チェックで再発防止へ 富山・小矢部市
