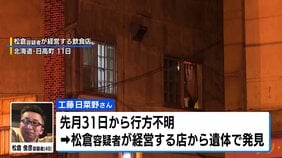(この記事は2022年9月の台風14号の際、台風の備えやマンションなどで想定しておくべきリスクについて専門家にインタビューしたものです)
(アナウンサー)自然災害を研究する鹿児島大学の井村隆介准教授です。今度の台風はやはり厳重な警戒が必要ですね。
●井村隆介准教授「警戒が必要というよりも、これまでに経験したことがないような台風が近づいている。ある意味で災害が起こることを前提に、それに巻き込まれないように注意をしていただく必要があるレベルだというふうに考えてもらえばいいかと思います。」
(アナウンサー)風もすごく強そうですね。
●井村准教授「陸上で最大瞬間風速が60メートル、海上で75メートルというのが、もうこれまでほとんど経験がないですね。」
【2018年に近畿を襲った台風より「上」の予想】
●井村准教授「2018年に近畿地方を襲った台風では、関西空港のところに船がぶつかって関西空港に閉じ込められてしまったことがありました。けれども、あの時が海上で75メートル、陸上でも60メートルぐらいの風だという風に考えられたんです。それが今回鹿児島では、ちょうど方向を変えるあたりなので、18日未明から19日未明にかけて、そういう状態が続くかもしれないっていう予想が出ています」
【暴風の時間が非常に長く続く?1日停電のおそれも】
(アナウンサー)予想でいうとやはり長時間に?
●井村准教授「方向を変えるところなので、スピードがどうしてもゆっくりになる。その分だけ直撃っていうのもあるんですけれども、暴風圏を抜けるのが非常に時間がかかるということですよね。そうすると、もし停電が起こったときに、普通の風であれば10分20分で解消するかもしれないんですけれども、暴風が去るまでなかなかその解消できないということで、1日、停電続くかもしれない。」
【長時間停電のリスク】
●井村准教授「窓も閉め切っているような状態でエアコンが使えないということになると、熱中症の恐れがあるわけですよね。だから、水分を用意しておくとかということも大事ですし、電気が途絶えると、うちわとかそういうものしか使えません。」
「冷蔵庫も24時間ぐらい止まってしまうと、もう冷凍室のものとか冷蔵室のものというのが食料として置いておいたはずなのに…っていうようなことになってしまいます」
【時速200キロ超で洗濯バサミが飛んでくる?】
(アナウンサー)風速60メートルとかいうのは体で感じたらどれぐらい?
●井村准教授「秒速30メートルぐらい大体108キロぐらいになるんですけれども、秒速60メートルというと、もう200キロを超えるような状態ですね。そうするともう本当に転んでしまうし、大きなトラックでも倒れてしまう。ベランダに置いてあるような洗濯バサミが飛んでも、時速200キロで飛ぶわけですから、けがをするとか、場合によっては命にかかわってくるようなことが起こってしまうということです」
【マンション高層階で死者も窓を保護して離れて過ごす】
(井村准教授)「2018年に近畿を襲った台風では、マンションの8階にいる人でも物が飛んできて、窓ガラスを突き破って、部屋の中で亡くなった事例がありました。」
「今は雨戸やシャッターのないマンションとかに住まわれてる方もいらっしゃると思います。飛んできたもので、割れてしまって飛散ということもありますので、シートをかぶせたりとか、あるいは養生テープ、さらにはカーテンを閉めて、一番接近して風が強いようなときには窓から離れて過ごすということも重要になってくるかと思います。」
(アナウンサー)避難を考えていらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、それも今日のうちに明るいうちに避難された方がいいという?
●井村准教授「暗くなってからでは、周りの状況も見えないですし、もし物が飛んできたとしても見えない。雨が強くなってくると、もう本当に周りが見えない」
【雨量200ミリでもがけ崩起こるのに、予想は500ミリ以上】
●井村准教授「予想されている雨量が400ミリとか500ミリとかとんでもない予想されているんですけども、もしその半分の雨200ミリであっても、普段ではもう本当に崖崩れとかが起こる状態なんです。」
【木が揺すられて少しの雨でもがけ崩れが】
●井村准教授「台風のときには普通の雨とは違ってですね、木が揺すられちゃう。木が揺すられてると、少しの雨でも今まで崩れなかったようなところでも弱くなって崩れたりというようなことがあります。洪水だけでなく崖崩れというのに関しても、台風っていうのは特別な警戒が必要ってことになってきます。」
【「災害起こること前提で、今できることを考えて」】
●井村准教授「もう災害が起こることを前提に、それに巻き込まれないためにはどうすればいいのかっていうようなことを考えていただくレベルの台風が近づいているんだということを、自分で確認して、今できることを考えてやっていただきたいなと思います。」