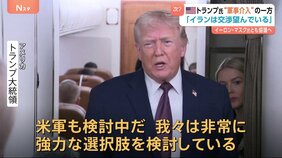◆「揚げかまぼこ」が「てんぷら」や「さつま揚げ」と呼ばれる理由
では、その「揚げかまぼこ」が、なぜ「てんぷら」や「さつま揚げ」と呼ばれているのでしょうか。
ルーマニア国立交響楽団の常任指揮者で、日本料理の歴史や文化を研究している尾崎晋也さんに取材しました。
日本料理の歴史を研究 尾崎晋也さん
「昔、沖縄の漁師が、東南アジアで作られていた魚のミートボールを揚げたものを見て、それをまねて作ったものが“チキアギ”。『さつま揚げ』の原型と言われている」
東南アジアの料理をまねて作った沖縄料理「チキアギ」が、今の鹿児島・薩摩に伝わり「つけ揚げ」になったそう。

さらに、それが江戸に伝わり「薩摩のつけ揚げ」と呼ばれましたが、短く省略されて「さつま揚げ」になったと考えられています。
そして、ややこしいのが大阪で呼ばれている「天ぷら」という呼び方です。
日本料理の歴史を研究 尾崎晋也さん
「こういう本がある。『守貞漫稿』。京都・大阪・江戸の違いについて書かれていて、関西では“さつま揚げ”のことは“天ぷら”と呼ぶ、“天ぷら”を“つけ揚げ”と呼ぶ。非常に混乱します。つけて揚げるから“つけ揚げ”なんだと思います」
実は、江戸で「さつま揚げ」と呼ばれていたものを、大阪では「天ぷら」と呼び、江戸で「天ぷら」と呼ばれていたものは、大阪で「つけ揚げ」と呼ばれていたのです。
というのも、大阪では油で揚げた料理全般を「天ぷら」と呼び、特に衣を付けて揚げる「天ぷら」を、「つけ揚げ」と呼んでいたようです。
日本料理の歴史を研究 尾崎晋也さん
「明石焼きを明石では“明石焼き”と言わない。“玉子焼き”という。そんな感じですね」
つまり、地域によって名前が違うのは、各地の歴史や文化が反映されているからなのです。
【調査結果】
北海道の「かまぼこ」、東京の「さつま揚げ」、大阪の「天ぷら」は、基本的には同じ食べ物!
他にも、同じものでも名前の違う食べ物の代表が…「おやき」
北海道では「おやき」と呼ばれている食べ物ですが、東京では「今川焼き」、大阪では「回転焼き」と、地域によって呼び名が違う食べ物は、色々あるんです。
もんすけ調査隊では、視聴者の皆さんのギモンや地域の問題について調査していきますので、ぜひ、投稿をお寄せください。