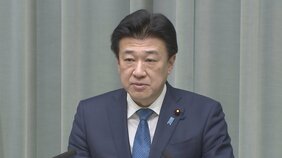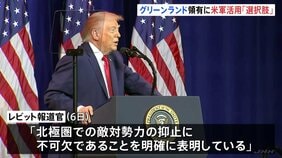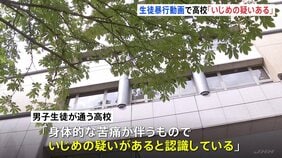「遺体の首を切断して持ち運ぶ」という事件の特異性から、「犯行当時の心理状態が事件にどう影響したか、慎重に調べる必要がある」。それが理由でした。
元東京地検検事の中村浩士弁護士は、長期の鑑定の理由をこう想像します。

元東京地検検事 中村浩士弁護士
「同じ先生が3人を鑑定しているという前提での鑑定留置請求ではないか。通常の1人を相手にする鑑定より、やはり時間がかかるというのは、合理的だし、うなずける話しになってくる。そういったところを検察としては主張したのかな」
では、鑑定留置とは、一般的に、どのように行われるのでしょうか?

北大病院附属 司法精神医療センター 賀古勇輝(かこ・ゆうき)センター長
「北大病院の場合は、原則として病院には入院させないで、警察署ないし拘置所にいるところに通って診察する場合が多い。特殊なことをするわけではなく、病院で行う診察とそれほど変わらない。病院であれば患者さんですけど、鑑定の場合は、被疑者や被告人。面接して、いろいろお話しを聞いて、その人に精神的な病気があるかどうかを判断することになる。病院で行う診察よりは、10倍くらいの時間をかけて念入りに行う」

鑑定は、病院で行われる診察と変わらないといいます。
また、回数も日常業務の合間に行われるため、週に1~2回程度だと明かします。
北大病院附属 司法精神医療センター 賀古勇輝(かこ・ゆうき)センター長
「普通の仕事がある傍らでやらなきゃいけないのですごく大変。毎日診察する余裕が、精神科医にないことが多く、大体週に1~2回の診察」