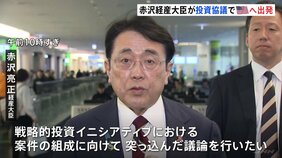7年ぶりに噴火した霧島連山の新燃岳。噴火から1か月が経過し、生活への影響が続く中、今後の火山活動はどうなるのでしょうか。火山地質学が専門の鹿児島大学の井村隆介准教授に聞きました。
新燃岳の現状と生活への影響
Q(岡田キャスター):現在の新燃岳の活動をどのように見ていらっしゃいますか?
A(井村隆介准教授):噴火活動から1か月ほど経ち、天候で見えにくい状況もありますが、少し落ち着いている状況なのかなと思っています。

Q(岡田キャスター):噴火による生活への影響が出ています。この状況についてはいかがでしょうか?
A(井村隆介准教授):現在、新燃岳で起こっている噴火は火山学的にはとても小さな噴火です。しかし、火口の南側に積もった大量の火山灰が、雨によって霧島川の支流に流れ出し、麓の田んぼの水が使えなくなっています。
また、温泉を引いている配管が土石流で壊されたため、霧島神宮周辺や温泉街で温泉の供給が止まっています。雨が降ると土石流の危険があるため、復旧にはまだ時間がかかるかもしれません。
Q(岡田キャスター):新燃岳そのものは、このところ噴煙の量が少し減っているように感じますが、いかがですか?
A(井村隆介准教授):天候で見えない部分もありますが、7月初めに噴煙が5000mまで上がったような状況から比べると、落ち着いてきている感じはあります。
Q(岡田キャスター):このまま落ち着いていくとは限らないということでしょうか?
A(井村隆介准教授):そうですね。地震の回数は減っていますが、新燃岳は過去に大きな噴火を起こしてきた火山ですので、注意が必要です。