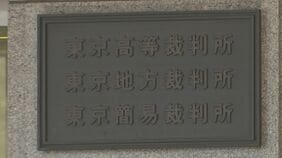錦江湾奥の姶良カルデラでおよそ3万年前に発生した巨大噴火で噴出した火砕流の分布図です。鹿児島県内の広い範囲に及んでいます。

火砕流の堆積物「シラス」の埋蔵量は750億立方メートルとも言われ、東京ドーム6万個分に相当します。
崩れやすいことから「厄介者」とも言われるシラスを、「夢の資源」にしようという研究が進んでいます。
垂水市にあるシラスの採取場です。シラスを削り出し、建築の材料や農業用の資材に加工して販売しています。

県本土のおよそ半分を覆っているシラスは崩れやすく、大雨が降ると土砂災害を引き起こす一因となります。鹿児島では「厄介者」とも言われるシラスを有効活用できないか、研究が続けられてきました。
(県工業技術センター研究主幹・袖山研一さん)「砂、粉に見えるのがガラス質。色のついた粒子が結晶質。軽石とか粉分を粉砕してセメントの代わりの混和材に使う研究」
シラスを手にするのは県職員の袖山研一さんです。シラスを、コンクリートの原料となるセメントの代わりとして使う研究に取り組んでいます。
(袖山研一さん)「シラスからつくられた火山ガラス微粉末がコンクリート二次製品や生コンクリートに使える状況に来た。未来につながる夢の資源となる」
研究拠点は霧島市にある県工業技術センターです。

(記者)「鹿児島では厄介者とも言われているシラス。シラスから取り出した細かい粉末が鹿児島、日本の工業を変えるかもしれません」
シラスをセメントの代わりにするためには、ひと手間もふた手間もかかります。シラスは火山ガラス、砂の結晶、軽石、粘土からできています。この中からセメントに必要な火山ガラスと軽石だけを取り出すことが必要です。
こちらが成分を取り出す実験用の装置です。4つの成分は重さが違うため、下から空気を送りそれぞれを分離させることで、シラスから火山ガラスと軽石だけを取り出します。
そして、この2つを混ぜあわせ砕いた細かな粉末がセメントの代替品「火山ガラスの微粉末」です。大きさは5ミクロン。髪の毛の太さの20分の1です。

2つの機械を使って100キロのシラスから65キロ作れるということで、1日に120キロ製造できます。企業とおよそ6000万円かけて開発したこちらの装置が軌道にのるまでには、7年かかりました。
装置が今後実用化されれば、1日に、これまでの1万倍以上の1440トンの原料が製造できる見込みで、県内外の企業が事業化を検討しています。
(袖山研一さん)「頭では理解していても、装置としてやってみるとうまくいかない。いろいろな機械を試しても、なかなか思うようにいかないというのがずっと続いていて。全国を飛び回って、やっと装置と技術にたどり着いた」
袖山さんによると「通常のセメントの分量の1割から2割を置き換えることで、強度や耐久性が高まる」ということで、シラス由来のセメントは着想から34年でこれまでに4件の特許を取得しました。
九州には現在、セメント製造工場が福岡と大分にしかありませんが、今後「シラス由来のセメント代替品」が普及した場合、年間21億円の売り上げが見込めるといいます。
(袖山研一さん)「なかなか成果が出ないときにはへこんだが、莫大な量が目の前、足元にあるので、これがもし工業材料に変われば、一挙に若い人たちのシラスを見る目が変わるだろう」

シラスの利活用は温暖化対策としても注目されています。セメントの製造過程では石灰を高温で焼く時に大量の二酸化炭素が発生します。1トンつくるのに、0.8トンの二酸化炭素が出されるとも言われ、その量は年間3800万トン、日本全体のおよそ4%に相当します。
「脱炭素」の流れが広がる中、セメントの一部をシラスに置き換えることで、二酸化炭素の排出量を抑えられることもあり、その市場規模は鹿児島だけにとどまりません。

(袖山研一さん)「シラスはロマン。足元にある資源。火山灰とかあまりいいイメージを持っていない人も多いかもしれないが、これが工業資源として利用できれば地方創生の起爆剤になる」
研究を始めて34年。袖山さんは今年度で定年退職の予定ですが、後継者も育っています。
(袖山研一さん)「研究の虫。研究に懸ける情熱はすごい。僕はシラスに懸けているが」
(主任研究員・樋口貴久さん)袖山主幹のこれまでの実績に勇気づけられ、一緒に楽しくシラスの未来に向けて研究している」
シラスの活用の幅を広げてほしいと、県内の企業も期待します。
(シラス採取する清新産業・清永敏宏工場長)「研究開発してもらったことをもとに、さまざまな分野の客にシラスを展開したい。一般の人に厄介者ではないということをあらためて認識してもらい、シラスを有効活用できるものとして認知してもらえるよう努めたい」
シラスをセメントに代える研究は実用化への一歩を踏み出したばかり。「夢の資源」は私たちのすぐそばにあります。