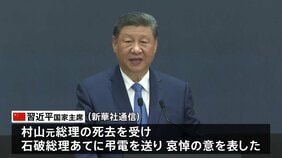今月16日は敬老の日です。ニューズナウでは敬老の日を前に、元気なお年寄りを紹介するシリーズ「きばっちょいもす」をお送りしています。2回目は、染物ひとすじ55年。81歳の男性です。
鹿児島県いちき串木野市。ここに明治2年、1869年創業の老舗があります。
亀崎染工。代々、染物を家業としてきて、ことし創業155年。大漁旗や五月のぼり、法被などの制作を手掛けています。
亀崎洋一郎さん、81歳。息子の昌大さんが5代目を継いでからは会長となりました。しかし、その姿はいまも作業場にあります。現役の職人として一線で働いています。

(亀崎洋一郎さん)「55年ぐらいになるかな。うちの染物の仕事は、昔から手染め。これから何年経っても同じような工程で染めるしかない」
ことし1月、鯉のぼりと一緒に掲げる「五月のぼり」の制作がはじまりました。
いくつかの工程があります。まず、のぼり旗の絵柄を切り抜いた型紙を布の上にはります。そして、その上から糊を伸ばしていきます。
糊付けされた絵。その上に砂を散らして糊を固めます。これを天日干しして、糊と砂が固まると、絵柄に沿った枠ができるのです。
3月。絵柄に色を塗る工程に入りました。五月のぼりの絵柄は、桃太郎や武将の加藤清正、のぼり龍など。1枚の図柄に使うのは、およそ20色。枠ごとに色を塗り分けます。
(亀崎洋一郎さん)「梅雨時とか、雨の降る日は思うような色が出ない。天気に左右されることが一番、大変」

そして水洗いして糊と砂を落とすと、くっきりと絵柄が浮かび上がります。天日干しした「のぼり」が春風に揺れます。
(亀崎洋一郎さん)「自分たちができる、めいいっぱいのことが、ひとつの作品に入れ込んでいく。入れ込んだときに、いい作品ができたら、いいものができたと報告ができる」
8月。亀崎染工では、大漁旗の制作が始まっていました。
大漁旗は「大漁」の文字と船の名前を大きく配置して、縁起が良いとされる鶴や亀の絵柄がよく描かれます。五月のぼりと同じように丁寧な仕事が続きます。
(亀崎洋一郎さん)「家を継いで50何年たつが、いまも試行錯誤して描いている」
(息子・昌大さん)「厳しい父親というイメージ。仕事に対しては常に自分のことよりも、最優先で技術にとにかく向き合って習得することに時間を割いてきた。そういうところが、学ぶべき点」
仕事の合間、自宅の植木の手入れに汗を流します。
(亀崎洋一郎さん)「仕事中心に体を動かしているのが、健康の源。世界一の妻がいる。料理が上手で、美味しく食べていることが健康の秘訣」

(妻・久美子さん)「真面目な人。芯は通っている、一本。好き嫌いなく、よく食べてくれる。今のままでいてくれたらいい」
染物ひとすじ55年。いつものように工場には仕事に打ち込む亀崎さんの姿があります。