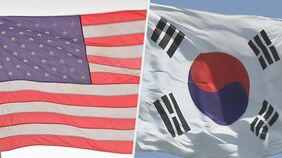岩手県大船渡市で起きた大規模な山林火災は、7日で発生から10日目を迎えました。今回のような大規模になるおそれも多い山火事。出火原因の多くは火の不始末によるもので、この時期、山間部では注意が必要です。
暗闇の中、山の斜面を焼く炎。3月1日に岩手県大船渡市の山林火災の現場で消火活動にあたった、福島市の消防隊が撮影した映像です。
2月26日に発生し、発生から10日目となったこの山林火災。これまでにおよそ2900ヘクタールを焼き、依然、鎮火には至っていません。福島市消防本部によりますと、2月から3月にかけては特に山火事が発生しやすい季節だといいます。
福島市消防本部 予防課・二瓶貴文主査「とても空気も乾燥するし、風も強くなる。火災にはとても注意が必要な時期」
今回のように大きな規模にも発展しかねない山火事ですが、その多くは「小さな火の不始末」が原因です。
二瓶さん「たき火や火入れ、たばこの投げ捨てなどによる火の不始末、それから不注意などの人為的な要因によるものが非常に多い」
林野庁によりますと、2018年から5年間の間に国内で発生した林野火災の出火原因は、たき火が最も多く、全体の3割以上、次いで火入れがおよそ2割。たばこや火遊びなどを加えると、全体のおよそ7割が「人為的な要因」です。
二瓶さん「(山林は)落ち葉や枯れ草が堆積しているので、ひとたび火が付くと延焼拡大しやすい。県内でも山がたくさんある。1人1人が火の取り扱いに注意すること、必ず消火を徹底することが必要」
また山林火災は地形の問題などからほかの火災と比べて消火活動が極めて難しいことも延焼が広がりやすい一因だということです。山林火災のきっかけを作らないためにも、火を使った際には、その「後始末の徹底」が必要です。